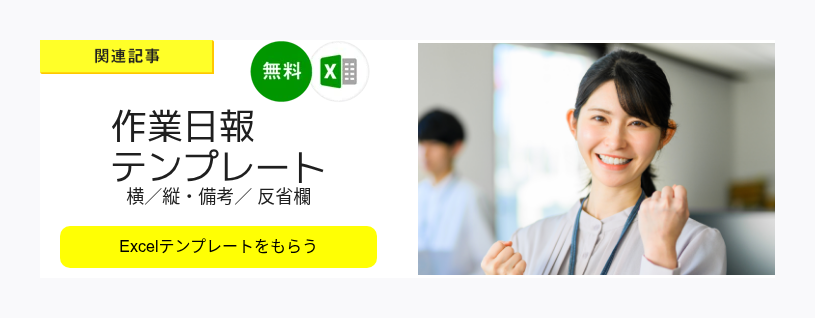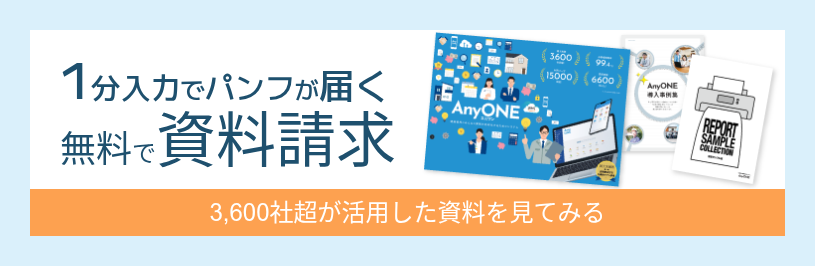【建設業】請求書の正しい作り方と書き方|必須項目・テンプレート・送付方法まで解説

建設業の人手不足の原因は5つ!対策して2025年問題に備えよう
近年の人口減少とともに、少子高齢化という流れが既成事実となり、多くの業種で人手不足が常態化しつつあります。
特に他業種に比べてハードなイメージがある建設業は、若年層の新規就労者が少なく、女性の入職も進んでいるとは言えません。
これに対して建設業の需要は、更新時期を迎えているインフラの改修や改築、古い建築物の修繕や耐震化などを中心に伸びているのが現状です。
そのため、現在の慢性的な人手不足は、建設業にとって、より深刻なものとなっています。
また2025年には、従業員の高齢化により大量の退職者が出て建設業の労働人口が約90万人不足すると予測されており、人手不足を早期に解決する必要があります。
この記事では、建設業の人手不足の要因と対策の事例について解説しています。ぜひ最後まで読んで参考にしてください。
INDEX
建設業が人手不足に陥っている原因
建設業が人手不足に陥っている理由は、大きく5つ挙げることができます。少子・高齢化の拡大、給与・待遇の不安定、3Kのイメージの定着、建設業の需要が増加の4つです。
それぞれについて説明します。
少子・高齢化の拡大
総務省統計局によれば、の人口は2008年にピークとなり、2011年以降12年連続で減少しています。直近の2021年10月から2022年9月までの1年間では、55万6千人(‐0.44%)の減少となっています。
人口減少の影響で、さまざまな業種で就業者数が減少していますが、中でも大きな影響を受けているのが建設業です。
国土交通省が公表している統計では、建設業就業者数は令和2年で492万人ですが、これはピーク時の平成9年から約28%の減少となっています。
(参考:国土交通省|建設業を巡る現状と課題)
さらに建設業では、高齢化も顕著となっており、令和2年時点で55歳以上が約36%、29歳以下は約12%です。また2025年には、高齢化による大量の退職者が出ると見込まれており、状況は深刻です。
この少子・高齢化は今後も続くとされているので、できる限り早い段階での対策が必要となっています。
給与・待遇が不安定
建設業が人手不足に陥っている要因の一つに、給与や待遇が不安定なことが挙げられます。
建設業界では、給与を日給制にしている会社が多く、天候が悪くて現場が中止になると給料が下がることになります。
建設業は、他業種に比べると、繁忙期と閑散期での仕事量の差が大きいというのも不安定要素の一つです。公共工事などが多い年末や年度末が忙しく、4~6月は暇になります。
建設会社によっては、現場がなく仕事がない期間は休業状態になるということも少なくありません。逆に繁忙期は、残業が増えるということもあります。
また、下請での施工が多い建設会社は、元請の受注具合で仕事量が決まるということもあるでしょう。
2021年の建設業の年間労働時間は2032時間で、全産業の平均1709時間に比べて323時間も長いです。
以上のような不安定要素は、施工管理などの資格があり実務経験がある正社員待遇の方よりも、経験の浅い若年層に多く見られるので人手不足解消のためには早急の対策が必要です。
(参考:日本建設業連合会|建設業の担い手働き方の現状)
3Kのイメージの定着
以前から建設業は、3K(きつい、汚い、危険)の代表格のように言われ、それが現在も定着しています。
スコップやピックを手に硬い地面を掘り起こす、外で重い材料を運び続け泥や埃まみれになる、トンネルやダム工事の発破作業を行うなどのイメージです。
このようなイメージが色濃く残っている建設業ですが、現在では、さまざまな先進技術が現場に導入されて格段に効率化しています。例えば、高機能な建設機械や特殊車両、AIやICTを活用したシステムなどです。
もちろん、すべての人力作業が無くなったわけではありません。ただ建設業という業種の中にも、さまざまな現場や部署があり、3Kとは無縁の分野が広がっていることは間違いありません。
この現状を、これまで建設業になじみが薄いとされてきた、女性や若年層の方にアピールしていくことが重要だと考えられます。
建設業の需要が増加
近年、建設業の需要は明らかな増加傾向にあり、人手不足に拍車をかけているのが現状です。
現代社会は成熟期を迎え、施設や設備が飽和状態となっているから、新規の建設工事は少なく需要は伸び悩んでいると思われがちです。しかし、現状はその逆となっています。
まず、高度成長期に建設されたインフラが更新の時期を迎えており、改築・修繕、耐震化工事などの需要が伸びていることが挙げられます。加えて道路や鉄道などの定期的な維持工事も必要です。
また経済的・文化的に知名度の高い日本では、各種の国際的なイベントが行われるため、そのための建設工事が行われてきました。
そして自然災害も多く、災害復旧や災害防止のための改良工事を止めるわけにはいきません。
このような理由で建設業の需要が増加しているため、さらなる人手不足を招いています。
円安による外国人労働者の不足
日本では、建設業に限らず、人材不足対策として外国人労働者を受けいれていますが、昨今の円安で大きな影響を受けています。
日本に来て働いている労働者の多くは、自国よりも給与が高い日本で働くために来日していますが、円安のためメリットが薄れているのが現状です。
またかつて発展途上国と呼ばれていた各国の経済成長が進み、日本との経済的格差が縮小する傾向にあるためなおさらです。
たとえば外国人労働者で一番多いのはベトナムの方ですが、2019年9月の就労時には1円当たり約220ドン(ベトナム通貨)だったのが、2022年10月は162ドンにまで目減り(‐26%)しています。
自国の家族への送金が主な目的の彼らにとって、円安の問題は非常に切実なものだといえるでしょう。
人手不足対策の事例
建設業界では、長引く人手不足の深刻化に加えて、2025年には高齢化による大量退職者が出るという問題もあり、人手不足対策が官民挙げて行われるようになっています。
ここでは、代表的な7つの事例を取り上げ、それぞれの概要を説明します。
ICT技術・ITの導入で生産性を向上
建設業界では、人手不足の解消と新規就労者の入職を目指して、積極的にICT技術を導入し始めています。その中でも最も注目を浴びているのが「ICT施工」です。
ICT施工では、設計や測量調査から、実際の施工や施工管理までデジタル技術を活用します。
たとえば設計では3D設計データの自動生成、測量調査では3Dレーザースキャナー測量などが大幅な省力化と高精度の成果品を生みだしています。
施工ではICTが建設機械の位置情報と遠隔操作を連携し、施工管理ではウェアラブルデバイスが活躍中です。
このような技術の導入は現場の省人化と同時に、建設現場の労働環境を改善し、新規就労者の興味と関心をひき付けています。
適切な工期の設定
合理的で適切な工期を設定し、無駄のない効率的な人員配置ができれば人手不足対策になります。
建設現場には一つとして同じ現場はなく、それぞれの現場が抱える条件によって工期は違ってきますが、必ず最適な工期というのはあるものです。これまでのやり方をただ繰り返すのではなく、その現場に最適な工期を追求していくことが重要です。
新しい工法や建設機械、最新機器を導入することで、省人化した工期を設定することは有効な人手不足対策となっています。
給与・福利厚生の改善
新規就労者、特に若年層の人材が増えるような取り組みとして、重要なものの一つが給与・福利厚生の改善です。
日給制を月給制に変更することを含め、通勤費(交通費)や皆勤手当、資格取得手当など、各種手当の導入による実質賃金のアップも検討する建設会社が増えています。
また大手に比べると中小規模の会社は給与・待遇が悪いとされますが、地元密着型の利便性や、就労者一人ひとりに寄り添った対応や配慮があるなどの利点についてアピールして成功している会社も多いです。
業界イメージの向上
建設業界は、3Kに象徴されるように、過酷な労働環境や危険作業などのイメージが先行しています。新規就労者を獲得するには、このイメージの払拭が必要です。
過去には、国土交通省による「建設業イメージアップ戦略実践プロジェクト(CIU)」がありました。先進的な技術を取り入れて体力的・精神的な厳しさは軽減されていることや、働き方改革の実例を各種メディアで発信するプロジェクトです。
また安全性を考えて現場と第三者を遮断してしまいがちな建設業ですが、明るさや親しみやすさを感じる現場ごとのイメージアップ戦略も工事予算に組み込まれるようになっています。
女性の雇用を増やす
これまで女性に敬遠されがちな業界を、ITの導入や福利厚生の充実などにより変えていこうという動きが本格化しています。
女性のライフイベントを考慮した柔軟な働き方、ICT施工を支えるオフィスワーク分野の拡充、施工管理者の長時間労働を軽減する女性建設ディレクターの誕生などが実例です。
また女性専用のトイレや更衣室、清潔な休憩室、女性同士が交流できる場の創出などは、大手ゼネコンだけでなく中小規模の建設会社でも実践されるようになっています。
女性が活躍している職場は、働く環境が整い、コミュニケーションも活発になりやすいと評価されています。
建設キャリアアップシステム
建設業は社会を支える重要な産業であり、今後も安定的に発展な必要ですが、建設業の技能者は高齢化が進み3分の1は55歳以上となっています。
新たな就労者の入職や定着に向けて、国土交通省と厚生労働省が連携して推し進めているのが「建設キャリアアップシステム(CCUS)」です。
建設キャリアアップシステとは、建設業の技能者の保有資格や社会保険加入状況、現場の就業履歴などを登録・蓄積して業界横断的に活用する仕組みを指します。
技能者の職務経歴や現場実績を「見える化」することによって、適正な処遇改善につなげることで、若い世代が安心して働き続けられる建設業界を目指すものです。
外国人労働者の受入
建設業に限らず、国内で人材を確保することが難しくなっている産業では、外国人労働者の受入は人材不足対策で大きなウエイトを占めています。
特に2019年4月に「特定技能制度」が、新たな外国人材受け入れの手段として期待されています。これまでの「技能実習制度」は、あくまで国際協力が目的で、労働力の確保が目的ではありませんでした。
特定技能には、1号と2号の2種類あります。特定分野で相当程度の技能がある就労者が1号で最長5年の在留資格、2号は高度な技能を持った熟練者で在留期間に上限は設けられていません。
特定技能制度には一定の受け入れ条件などがありますが、長期的な雇用が可能なため、企業にとって貢献度の高いものとなっています。
AnyONEで人手不足対策
業務を効率化し、人手不足対策するなら工務店向け業務効率化システム「AnyONE」の活用がおすすめです。AnyONEは、下記の業務に対応しており、あらゆる工務店業務の生産性を向上させ、省人化に貢献します。
【AnyONEの機能】
●顧客管理
●工事・施工管理
●見積り・実行予算・発注
●入出金管理
●アフター管理
工事管理や実行予算管理、図面・写真管理などは、現場の人手不足対策に直結します。また現場技術者の属人化をなくすことにもつながるでしょう。
まとめ
本記事では、建設業における人手不足の原因と、対策として行われている事例について解説しました。
人手不足の原因は以下の5つです。
●少子・高齢化の拡大
●給与・待遇が不安定
●3Kのイメージの定着
●建設業の需要が増加
●円安による外国人労働者の不足
また、上記の対策として、生産性の向上と労働環境の改善、女性や若年層、外国人労働者の雇用促進など7つの事例を紹介しました。
このような対策を講じる際のベースになるのが業務全体の効率化であり、そのためにはツールの活用が必須になります。
最もおすすめする業務効率化ツールは「AnyONE」です。
ソフトの比較検討をしたい方は、下記の複数ソフトの『他社システムの機能比較』ボタンからぜひチェックしてみてください。
記事監修:佐藤主計
保有資格:1級造園施工管理技士、2級土木施工管理技士
建設業界に携わり30年。公共工事の主任技術者や現場代理人をはじめ、造園土木会社の営業マン・工事担当者として、数万円から数千万円の工事まで幅広く担当。施工実績は累計約350件にものぼる。