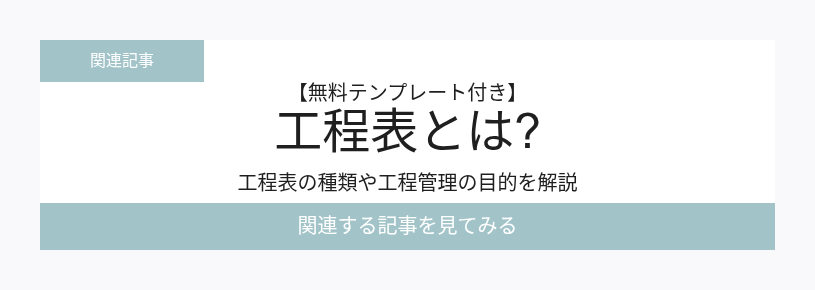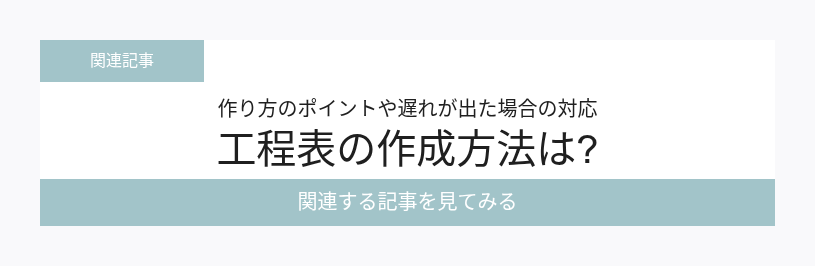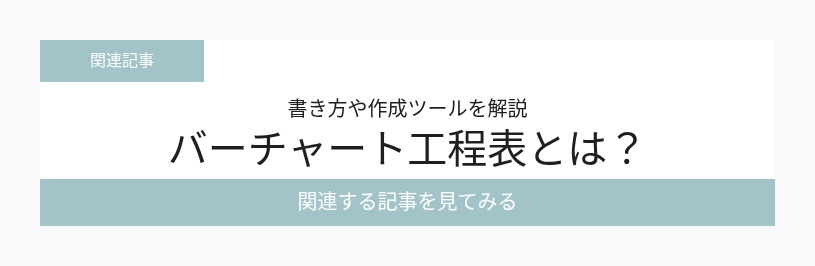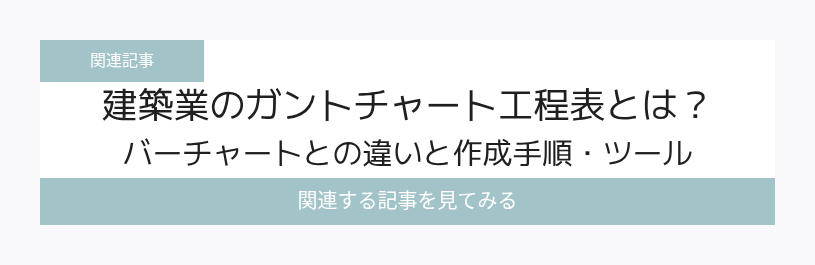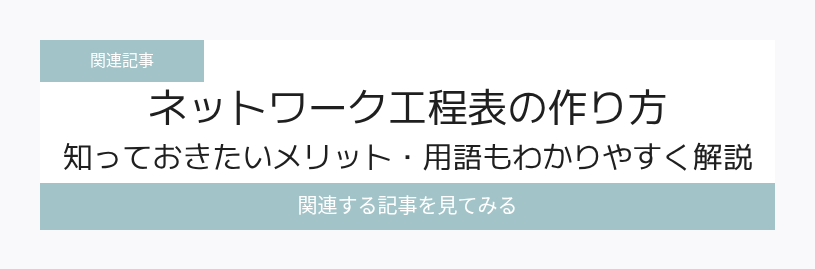建設業の経理とは?仕事内容から求められるスキル、会計システムの選び方まで解説

基礎工事とは?工事の種類や工程、失敗しない工程表の作成について徹底解説
建築工事において「基礎工事」は、建物を支える最も重要な工程のひとつです。基礎が不十分であれば、どれだけ立派な建物を建てても不同沈下やひび割れなどの不具合が発生し、品質や安全性に直結します。
そのため、工事を正しく進めるためには「基礎工事の工程表」が欠かせません。工程表は現場作業の段取りを明確にし、資材手配や人員配置を最適化する役割を果たします。
特に中小規模の工務店では、人材と時間の使い方が利益率を大きく左右するため、工程表をベースにした精度の高い管理が不可欠です。
本記事では、基礎工事の概要や種類、作業時のポイントをわかりやすく解説します。
INDEX
- 基礎工事とは?
- 基礎工事の種類は大きく分けて4つ
- 1.ベタ基礎
- 2.杭基礎
- 3.布基礎
- 4.独立基礎
- 基礎工事の各工程と手順
- 1. 地盤調査・地縄張り
- 2.遣り方(やりかた)工事
- 3.掘削工事(根切り)
- 4.砕石敷き・転圧・捨てコンクリート打ち
- 5.配筋工事・配筋検査
- 6.型枠設置・コンクリート打設
- 7.養生・型枠撤去
- 基礎工事の各工程で押さえておきたいチェックポイント
- 配筋検査
- コンクリートの品質
- 基礎表面のコーティング
- 基礎工事の遅延を防ぐには?
- 工事進捗を都度確認する
- 工程表の更新を怠らない
- 工程表の種類
- バーチャート工程表
- 失敗しない工程表作成と関連業者との連携
- 天候リスクを織り込んだバッファの設定方法
- 生コン・ポンプ車の手配と連携のタイミング
- 鉄筋、型枠大工など専門業者との調整ポイント
- ガントチャート工程表
- ネットワーク工程表
- AnyONEで基礎工事の工程管理を効率化
- 工程表を簡単作成
- 情報をリアルタイムで共有
- 工程変更や遅延リスクを即時反映
- 基礎工事に関するよくある質問
- Q1.基礎工事はどれくらいの日数がかかりますか?
- Q2.基礎工事の単価はいくらですか?
- まとめ
基礎工事とは?
基礎工事とは、建物の荷重を地盤に伝えるための基礎を構築する作業を指します。
基礎の主な役割は以下の通りです。

基礎は鉄筋コンクリートで作られ、底盤(スラブ)・立ち上がり・地中梁・杭 といった要素で構成されます。
これらの精度と品質が確保されていなければ、建物全体の寿命に影響します。
とくに日本は地震が多いため、基礎工事の出来不出来が耐震性に影響を与える要因のひとつです。適切に施工・管理された基礎は、建物の資産価値を守り、長期的な修繕コストの削減にもつながるため、基礎工事が非常に重要な工程であることがわかるでしょう。
基礎工事の種類は大きく分けて4つ
基礎工事の種類は大きく分けて以下の4つです。
- ベタ基礎
- 杭基礎
- 布基礎
- 独立基礎
それぞれメリットデメリットがあり、地盤の強さや建物規模に応じて工法が選ばれます。
各基礎工事の種類について特徴を解説します。
1.ベタ基礎
ベタ基礎は、建物の床下全面を鉄筋コンクリートで覆う工法です。面全体で荷重を支えるように作られたベタ基礎は以下のようなメリット、デメリットがあります。
【メリット】
- 不同沈下が起こりにくい
- 地震に強い
- 床下からの湿気を防げる
- シロアリ被害を抑制できる
【デメリット】
- 材料や残土処分などの量が多く、施工費が上がる
- 施工の精度が品質に影響を与えやすい
- 寒冷地では基礎を深くする必要があり、コスト増の要因になる
近年の木造住宅では最も多く採用されており、耐久性と耐震性を兼ね備えた標準工法といえます。
2.杭基礎
杭基礎は、地盤が軟弱な場合に採用される工法で、地中深くの「支持層」まで杭を打ち込み建物を支えます。
杭基礎は、以下の2種類に分けられます。
- 支持層まで到達させて荷重を直接伝える支持杭
- 杭の側面摩擦で荷重を支える摩擦杭
また、メリットデメリットは以下の通りです。
【メリット】
- 軟弱地盤にも対応可能
- 液状化対策になる
- 不同沈下を防げる
【デメリット】
- 施工コストが高い
- 振動、騒音が発生する
このように杭基礎は液状化対策や不同沈下の防止に有効で、中高層建築や重量の大きい構造物でもよく使われるものです。
ただし打ち込みに伴う振動・騒音が発生や、高度な施工技術が必要なため、周辺環境への配慮や地盤調査結果に基づいた適切な杭の選定が欠かせません。
3.布基礎
布基礎は、建物の柱や壁の下に連続して基礎を設ける工法です。他の基礎と同様にメリットデメリットを見てみましょう。
【メリット】
- コンクリートと鉄筋の使用量が少なく、比較的安価
- 寒冷地での施工でもベタ基礎よりコストを抑えられる
【デメリット】
- 湿気が溜まりやすい
- シロアリの被害を受けやすい
コンクリート使用量が比較的少なく、ベタ基礎に比べて施工費用を抑えやすいのが特徴です。古くから木造住宅に広く用いられ、地盤が比較的強固な土地に適しています。
ただし床下に土が露出するため湿気が溜まりやすく、シロアリ被害のリスクが高まる点には注意が必要です。
具体的には以下の方法で湿気やシロアリ対策をおこないます。
- 基礎と土台の間に通気用の基礎パッキンを敷く
- 換気用ガラリを基礎に設ける
- 土が露出している箇所に防湿シートを敷く
- 床下に土間コンクリートを打つ
換気や防湿対策をすることで耐久性を確保でき、適切な管理と組み合わせればコストと品質のバランスがとれる基礎工法です。
4.独立基礎
独立基礎は、建物の主要な柱の下にのみ基礎を設ける工法です。
独立基礎のメリット・デメリットは以下の通りです。
【メリット】
- 施工費用が大幅に削減できる
【デメリット】
- 耐震性や不同沈下には耐性がない
そのため独立基礎は強固な地盤や軽量建築に適しています。近年の一般住宅には採用されず、カーポートや物置、玄関ポーチの柱など限定的な部分に用いられます。
利用する際は地盤調査を入念におこない、安全性の確保が重要です。
基礎工事の各工程と手順
基礎工事は以下の工程を順に進めていき、安全性と精度を確保しながら工事をおこないます。

ここでは基礎工事の各工程について、代表的な手順と作業の流れを解説します。
1. 地盤調査・地縄張り
基礎工事に先立ち、まずは地盤調査をおこない、地耐力や沈下リスクを確認します。
地盤改良が必要な場合はここで対策を検討し、必要に応じて地盤改良をおこないましょう。
次に地縄張りをおこない、敷地に縄を張って建物の配置を示します。
設計図と現場をすり合わせる重要な工程であり、近隣との境界確認や建物の位置精度を確保する意味でも欠かせません。
2.遣り方(やりかた)工事
遣り方工事は、建物の基礎の高さ・位置・水平を示すための仮設作業です。
地縄張りよりも精度が高く、基礎の墨出しや型枠設置の基準となります。木杭や貫板を組んで基準線を設定するため、ここでの誤差が後の施工精度に直結するため、正確性が重要です。
このタイミングで基礎工事店、工事管理者、設計監理者など複数の目で配置確認をおこなう方法が理想的です。
水準器やトランシットを用いた正確な測量管理が求められる作業となります。
3.掘削工事(根切り)
設計図面に基づき基礎の深さまで地盤を掘削する作業です。基礎底面を平らに整えることで建物の安定性を確保します。
掘削中に地下水や既存配管が出てくるケースもあり、適切な排水処理や手掘り対応が必要になる場合もあります。
4.砕石敷き・転圧・捨てコンクリート打ち
掘削後に砕石を敷き詰め、ランマーなどの機械で転圧して地盤を締め固める作業です。
これにより基礎の沈下を防ぎ、安定した支持力を確保します。
防湿シートを施工する場合はこのタイミングで敷き、捨てコンクリートで押さえます。転圧不足は沈下や基礎割れの原因となるため、層ごとに均一に締め固めることが求められます。
5.配筋工事・配筋検査
設計図に従って鉄筋を格子状に組む工程です。基礎の強度を左右する重要な作業であり、かぶり厚さや鉄筋間隔、定着長さなど細部まで規定通りに施工する必要があります。
完了後は第三者機関や設計監理者による配筋検査を受け、合格しなければ次の工程に進めません。不備があれば補正し、再検査を経て適正な品質を確保します。
6.型枠設置・コンクリート打設
鉄筋を覆うように型枠を設置し、そこにコンクリートを打設します。基礎底盤(ベース)と立ち上がり部分を順に打設するのが一般的です。
打設時は気泡を除去し、コンクリートの材料が均一になるようにバイブレーターを使用します。この作業で密実なコンクリートを形成します。
7.養生・型枠撤去
コンクリート打設後は一定期間の養生をおこない、強度が十分に発現するまで保護します。一般に歩行可能になるまで3〜10日、強度が安定するには1か月ほど必要です。。
ブルーシートや散水で温湿度を管理し、ひび割れを防ぎます。養生が終わったら型枠を外し、仕上がりやアンカーボルト位置の確認をおこない、基礎工事が完了です。
基礎工事の各工程で押さえておきたいチェックポイント
基礎工事は後戻りが難しいため、各工程での検査が重要です。特に配筋やコンクリート品質など必須の確認項目を紹介します。

配筋検査
配筋検査は、鉄筋が設計図通りに配置されているかを確認する重要な検査です。
配筋検査では主に以下の点についてチェックをおこないます。
- 鉄筋の種類、径
- 鉄筋の間隔
- 鉄筋のかぶり厚さ(コンクリート表面から鉄筋までの距離)
- 各部継ぎ手の長さ
- 設備用スリーブの設置状況
- 補胸筋が必要な場合はその配筋状況
- ホールダウンアンカーボルトの設置状況 など
これらのポイントについて適切でなければ、基礎の耐久性や耐震性に大きな影響を及ぼす恐れがあります。検査は第三者機関や監理者がおこなうのが一般的で、不備がある場合は補修が必須です。
コンクリートの品質
コンクリートの品質は基礎の強度を左右します。打設前にコンクリートの配合計画書をもとに以下のポイントを確認しましょう。
- 呼び強度
- 粗骨材の最大寸法
- スランプまたはスランプフローの数値
- コンクリート、セメントの種類
- アルカリシリカ反応性の有無
- 水セメント比や単位セメント量、空気量、塩化物濃度の確認 など
打設時にはバイブレーターで空気を抜き、隙間のない密実な構造を確保することが重要です。
さらに打設後は適切な養生をおこない、急激な乾燥や温度変化を防ぐことで、ひび割れや強度不足のリスクを低減します。
基礎表面のコーティング
基礎表面のコーティングは、コンクリートの耐久性を高めるための仕上げ工程です。施工直後に散水やシートで水分を保持しつつ、表面に保護材を塗布することで、鉄筋の錆びや中性化を防ぎます。
さらに防水性を強化する役割もあり、床下の湿気や雨水による劣化を抑制します。長期的に強度を維持するうえで、欠かせない品質管理ポイントです
基礎工事の遅延を防ぐには?
基礎工事は天候や資材調達の影響を受けやすく、わずかな遅れが全体の工期に波及します。遅延を防ぐには、日々の進捗確認と工程表の適切な更新が不可欠です。ここでは現場で実践できる管理方法を解説します。
工事進捗を都度確認する
基礎工事は天候や地盤の状況によって影響を受けやすいため、日々の進捗確認が欠かせません。工程ごとに写真や日報を残し、予定との差異を早期に把握することで、手戻りや遅延を防げます。
特に配筋やコンクリート打設など後戻りが困難な工程では、現場監督や職長によるチェックを徹底することが重要です。小さな遅れでも放置せず、早期対応が遅延防止につながります。
工程表の更新を怠らない
工程表は一度作ったら終わりではなく、現場状況に応じて常に更新・共有することが重要です。雨天による作業中断や資材の納期遅れなど、想定外の事象は必ず発生します。
そこで工程表を逐次修正し、関係者全員が最新情報を把握できるようにすることで、無駄な待機や段取りミスを防止できます。クラウド型の工程管理システムを使えば、リアルタイムで反映可能です。
工程表の種類
工程表にはいくつかの種類があり、工事の規模や管理の目的に応じて使い分けることが求められます。
ここでは、建設現場で主に使用される代表的な工程表を紹介します。
バーチャート工程表
縦軸に「掘削」「配筋」などの作業項目、横軸に日付をとり、各作業の開始から終了までを棒グラフ(バー)で示した、一般的な工程表です。
どの作業がいつ行われるかが視覚的に分かりやすく、作成も比較的簡単なため、基礎工事を含む多くの住宅建築現場で基本の工程表として用いられています。
失敗しない工程表作成と関連業者との連携
優れた工程表は、単なるスケジュール表ではなく、現場を円滑に進めるためのコミュニケーションツールとなります。以下では、基礎工事を円滑に進めるためのポイントを解説します。
天候リスクを織り込んだバッファの設定方法
基礎工事は天候に左右されやすいため、工程表には必ず「予備日」を設定します。特に梅雨や台風の時期は、週に1〜2日程度の予備日を設けるなど、余裕を持った計画を立てることが、結果的に工期遵守に繋がります。
生コン・ポンプ車の手配と連携のタイミング
生コンとポンプ車は、打設日の1週間前には発注を確定させ、前日に再度時間と数量の最終確認を行うのが基本です。当日は、現場周辺の道路状況を考慮し、搬入ルートを事前に業者と共有しておくことで、スムーズな受け入れが可能になります。
鉄筋、型枠大工など専門業者との調整ポイント
各専門工事業者の入場タイミングは、工程表を作成する段階で確定させ、事前に共有します。特に、配筋工事完了後の検査日程や、型枠解体のタイミングは、後続の設備配管や土台敷きの業者との連携も必要になるため、常に最新の工程を関係者全員で共有する体制を築くことが重要です。
ガントチャート工程表
バーチャート工程表の一種ですが、各作業(バー)の関連性を矢印などで補足し、作業間の依存関係をより明確に示したものです。
「掘削が終わらないと砕石地業が始められない」といった前後関係が分かるため、バーチャートよりも詳細な管理が可能になります。
ネットワーク工程表
作業の関連性と順序を矢印と丸で結んでネットワーク図として表現する工程表です。この形式の最大のメリットは、工事全体の最短完了日数(クリティカルパス)を算出できる点にあります。
クリティカルパス上の作業が1日遅れると、全体の工期も1日遅れるため、どの作業を重点的に管理すべきかが明確になります。工種が多く、工程が複雑に絡み合う大規模な工事の管理に適しています。
AnyONEで基礎工事の工程管理を効率化
小規模工務店では、Excelで工程表を作成しても「共有できない」「修正が遅れる」といった課題が多く見られます。
そんな方におすすめなのが工務店向けの業務効率化システム『AnyONE』です。
工程表を簡単作成
AnyONEでは、誰でも直感的に工程表を作成可能です。
複雑なフォーマット調整は不要で、テンプレートを使えば現場に合わせたスケジュールをすぐに組み立てられます。紙やエクセルでの作成・管理に比べて作業効率が大幅に向上し、現場全体のスケジュール管理をスムーズに進められます。
情報をリアルタイムで共有
AnyONEなら、工事の進捗や資料を一元管理し、事務所のPC・現場のスマホどちらからでも確認可能です。わざわざ現場に出向かなくても最新の状況が把握できるため、不要な会議や報告業務の削減につながります。
また、現場写真や施工ファイルを物件ごとに整理して保存できるため、過去の資料も簡単に検索可能。情報共有がスムーズになり、社内外のコミュニケーションも効率化します。
工程変更や遅延リスクを即時反映
AnyONEでは、協力業者とも工程表や現場写真を共有でき、チャット機能でのやりとりも可能です。工程の変更や遅延リスクが発生した際も、その情報をリアルタイムに反映し、関係者全員に即時共有できます。
これにより工期のズレによる業者の重複や手戻りを未然に防止。進捗を「見える化」することで、現場と本社の連携が強化され、計画通りのスムーズな施工が可能になります。
基礎工事に関するよくある質問
「基礎工事にはどの程度の日数が必要なの?」「単価はいくらくらい?」といった、よくある質問を解説します。
Q1.基礎工事はどれくらいの日数がかかりますか?
一般的な木造住宅では4〜5週間が目安です。ただし天候や規模、基礎の種類などで工期は変動します。
Q2.基礎工事の単価はいくらですか?
坪あたり4〜13万円(1㎡あたり1.2〜4万円)が目安です。
まとめ
基礎工事は建物の安全を支える要であり、工程管理や品質確認を怠ると大きなリスクにつながります。
特に中小規模の工務店では、人員や時間の制約から効率的な管理が難しく、遅延や利益率低下の要因になりがちです。
『AnyONE』を導入すれば、工程表の作成や共有、進捗の修正までをリアルタイムでおこなえ、現場と事務所の連携が格段に向上します。
資料請求は無料ですので、まずはお気軽にご確認ください。
記事監修:望月尚文
不動産特化のWebライター。
総工費10億円規模のプロジェクトに従事し、施工管理の実務経験を積む。
その後、商社の建設事業部にて総工費3億円規模のビル改修やオフィス・店舗内装を手掛け、同事業部の立ち上げを主導。
現在は、2024年2月に株式会社Limitedを代表の吉田と共同設立し、内装工事の受注に加え、施工管理の派遣・人材紹介業務に関するコンサルティング事業を展開している。