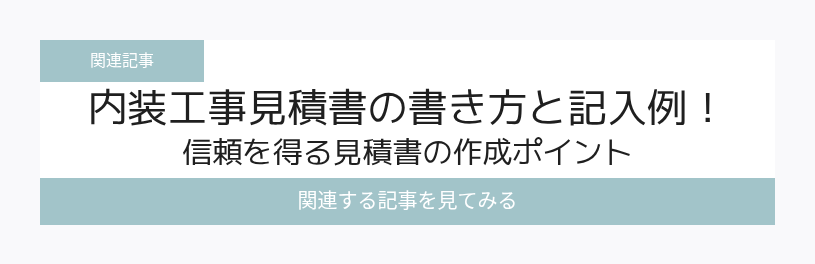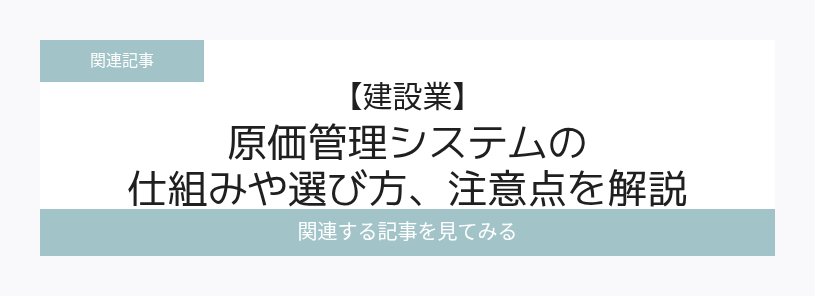建設業の経理とは?仕事内容から求められるスキル、会計システムの選び方まで解説

内装工事における原価率とは?計算方法・改善策を徹底解説
内装工事の利益を大きく左右するのが「原価率」です。材料費や労務費などのコストを正しく把握しなければ、利益が残らず経営を圧迫する原因となります。
今回は、原価率の基本的な計算方法から、コストが高くなる典型的な要因、改善のための具体策までを徹底解説します。
INDEX
内装業において原価管理が重要な理由
内装工事の利益を守るには、まず原価を正しく把握することが欠かせません。原価管理ができていないと価格設定が不安定になり、経営戦略の立案も難しくなります。
ここでは、原価管理がなぜ内装業にとって重要なのかを整理します。
価格設定の適正化
内装工事では、材料費や労務費が大きな割合を占めます。
これらを正確に把握しないまま価格を決めると、利益が出にくくなったり、逆に過度に高い見積もりで受注機会を逃すリスクがあります。
原価率を管理することで、工事にかかったコストと売上のバランスを数値で把握でき、適正価格を根拠をもって施主へ提示することが可能です。
施主に対しても「なぜこの金額になるのか」を明確に説明でき、信頼性向上にもつながります。
経営戦略
原価率の把握は経営戦略の根幹を支えます。
工事単位の利益を正しく把握することで、どの案件が利益を生み、どの案件が損失を生んでいるのかを明確にできます。
さらに、業界平均と比較することで自社の強み・弱みを分析でき、戦略的な改善に直結します。
例えば「小規模案件は利益率が低いが大規模案件では安定している」といった傾向を把握すれば、受注方針や人員配置の見直しに活かせます。
内装工事における原価率の目安と計算方法
原価率は「工事原価÷売上高×100」で算出され、工事原価には、材料費・労務費・外注費・諸経費などが含まれます。
日本政策金融公庫の「小企業の経営指標調査」(2024年8月実施)によると、内装工事の原価率は60%程度です。
ただし、業種や工事内容によって上下します。

【引用】「小企業の経営指標調査」(2024年8月実施)
※原価率については「売上高総利益率」をもとに算出しています。
例えば、特殊な材料を使う案件や工期が長期化する案件では原価率が高くなりがちです。正確な計算のためには、仕入れ価格や職人の作業時間を細かく記録することが欠かせません。
内装工事の原価率が高くなる原因とよくある課題
「利益が思うように残らない」と感じる背景には、原価率を押し上げる要因が潜んでいます。
材料費の高騰や職人の労務管理不足、見積もり漏れなどは多くの業者に共通する課題です。
以下では、代表的な原因を掘り下げて解説します。
材料コストが高い
材料費は工事原価の大半を占めるため、調達方法の違いが大きく影響します。
仕入れルートが限定的で競争原理が働かない場合や、都度発注で割高な価格になる場合はコストが膨らみます。
また、現場での端材ロスや余剰在庫も無視できないコスト要因です。材料の発注精度が低いと、無駄が積み重なり原価率が上がってしまいます。
労務コスト・職人管理の甘さ
職人の稼働効率が低いと労務費が膨らみます。段取り不足による待機時間や、仕様の確認不足から発生する手戻り作業、無駄な残業はすべてコストの増加につながります。
さらに、職人の技量差を考慮せずに配置すると、生産性が下がり工期が延び、結果として原価率が上昇します。
現場管理者が全体を把握できていないケースでは、こうした非効率が慢性化しやすい点も課題です。
見積もり漏れ・追加工事・仕様変更
見積もり段階での算出漏れや想定しない作業の発生は、利益を圧迫する典型的な要因です。
施主の要望変更や追加工事が発生した際に契約見直しを行わないと、工事費は増えるのに売上は増えない状況になります。
特に小規模業者では契約条項が曖昧なまま工事を進めてしまい、結果的に赤字案件になることも少なくありません。
内装工事の原価率を改善する方法
課題を把握したら、次は改善策の検討が必要です。
仕入れや工程の見直し、見積り精度の向上、さらに原価管理システムなどのITツールの活用による管理効率化など、取り組める方法は多岐にわたります。
ここでは実務に直結する改善方法を紹介します。
仕入れルートや材料選定の見直し
複数業者からの相見積もりや、まとめ買い・長期契約による価格交渉で材料費を削減できます。
また、現場ごとに必要な数量を正確に把握し、余剰在庫やロスを減らすことも重要です。
単純に「安い材料」ではなく、耐久性やメンテナンス性を考慮した「長期的にコスト削減につながる材料」を選ぶ視点も、利益確保には欠かせません。
作業効率を上げる
作業効率を高めることで労務費を削減できます。現場ごとに工程表を明確化し、役割分担を徹底することで無駄な待ち時間や重複作業を防げます。
さらに、標準化された手順を導入することで品質を維持しながら作業スピードを安定化できます。
ITツールを用いて進捗をリアルタイムで共有すれば、遅延や手戻りを未然に防ぎ、全体の効率が向上するでしょう。
見積り精度を高める
見積り段階での精度向上は、追加費用や漏れを防ぐ最も確実な方法です。
工事項目を細分化し、材料・労務・経費を一つひとつ積み上げて算出することが重要です。
過去の工事データを活用して実績ベースの数値を反映させれば、より現実に即した見積りが可能になります。
施主にリスクや追加費用の可能性を事前に説明しておくことで、トラブル回避にもつながります。
原価管理システム・ITツールの活用
従来の紙やエクセルでは、工事完了後にしか原価が分からないケースが多く、「気づいたときには赤字になっている…」ということもあります。
原価管理システムなどのITツールを導入すれば「実行予算→発注→支払」まで各段階で利益の推移を可視化できます。
これにより、予算超過が予測される時点で軌道修正が可能になり、赤字を未然に防げます。
デジタル化は業務効率化だけでなく、利益率改善の大きな武器になるでしょう。
AnyONEで内装工事の利益をリアルタイムで把握!
内装工事の原価管理を効率化するには、ITツールの活用が効果的です。
『AnyONE』は、工務店向けに設計されたクラウド型の業務効率化ツールで、実行予算の作成から発注・支払いまでを一元管理できます。
特徴は「各工程で利益がどのように変動しているか」をリアルタイムで可視化できる点です。
たとえば、発注単価の違いや現場での追加作業が即座に利益率へ反映されるため、経営者や現場責任者は早い段階で対応策を打てます。
さらに、スマホからも確認できるため、出先や現場でも最新情報をチェック可能です。進捗共有や資料作成の工数も削減でき、管理業務そのものが効率化されます。
AnyONEを導入すれば、原価率管理が「事後処理」から「リアルタイムの意思決定」に変わり、利益を守る強力な仕組みとなります。
原価率改善で注意すべき落とし穴と対策
原価率を下げようとすると、思わぬリスクが発生する場合があります。品質低下や職人の士気低下は、長期的な経営にマイナスです。
改善の取り組みを持続可能にするために、避けるべき落とし穴とその対策を確認していきましょう。
無理なコスト削減による品質低下・クレーム増加のリスク
コスト削減を意識するあまり、安価な材料を選びすぎると仕上がりの質が落ち、結果的にクレームや修繕対応によってコスト増になる場合があります。
短期的な削減ではなく、品質維持と両立できる方法を取ることが不可欠です。
職人のモチベーション・協力会社との関係への影響
人件費削減を優先すると、職人のモチベーション低下や協力会社との関係悪化を招きます。
結果として施工品質が下がったり、協力体制が崩れたりするリスクがある点に注意しましょう。
コスト削減と人材育成のバランスをとりながら進めることが重要です。
まとめ
内装工事の原価率は、利益を守り経営を安定させるための最重要指標です。材料費・労務費・見積もり精度といった基本要素を正しく管理することが、利益率向上の第一歩となります。
さらに『AnyONE』のような工務店向けの原価管理ツールを活用すれば、リアルタイムでコストを把握し、赤字リスクを未然に防ぐことが可能です。
原価率管理を徹底することは、価格競争が激しい内装業界で生き残るための必須戦略といえるでしょう。
AnyONEは資料請求だけでなく無料デモも可能です。使い勝手を実際に体験し、導入の参考にしてください。
記事監修:大﨑 志洸/株式会社Limited 取締役
兵庫県出身。施工実績は累計5,000件以上。
総工費10億円規模のプロジェクトに従事し、施工管理の実務経験を積む。
その後、商社の建設事業部にて総工費3億円規模のビル改修やオフィス・店舗内装を手掛け、同事業部の立ち上げを主導。
現在は、2024年2月に株式会社Limitedを代表の吉田と共同設立し、内装工事の受注に加え、施工管理の派遣・人材紹介業務に関するコンサルティング事業を展開している。