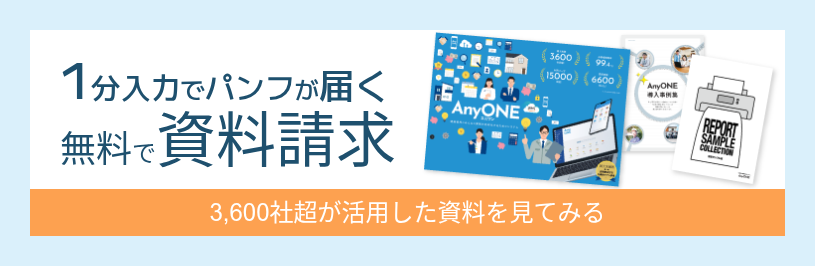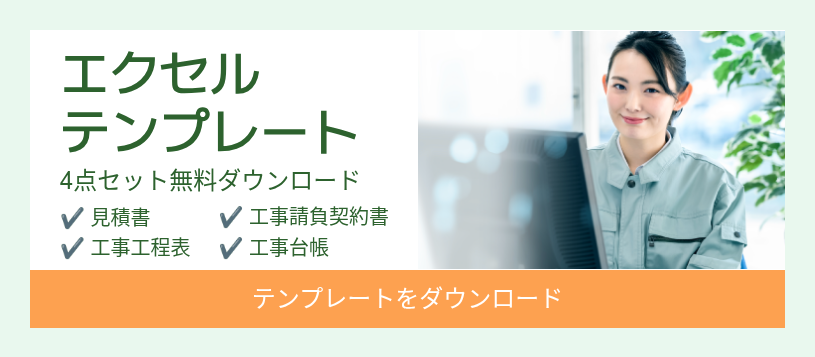屋根工事の工程表|作成時の注意点やチェックポイントを解説

内装仕上工事に建設業許可は必要?取得の要件・メリット・注意点を解説
内装仕上工事は、請負金額が小さい案件も豊富なため、建設業許可を取得せずに工事を受注している会社が多いです。
しかし、会社の規模を拡大させたいと考えるならば、建設業許可は欠かせません。
本記事では内装仕上工事の概要、内装仕上工事で建設業許可を取得するメリット・デメリット、取得のための要件について解説します。
業績を拡大させていきたいと考えている工務店やリフォーム会社の経営者は、ぜひ最後までご確認ください。
INDEX
- 内装仕上工事とは
- 内装仕上工事の内容
- 内装仕上工事の流れ
- 内装仕上工事で建設業許可を取得する3つのメリット
- ①公共工事の入札に参加できる
- ②規模の大きい内装仕上工事を請け負える
- ③会社の信用度が上がる
- 内装仕上工事で建設業許可を取得する3つのデメリット
- ①許可取得のために費用がかかる
- ②許可取得に手間がかかる
- ③取得後に維持のための手間と費用がかかる
- 内装仕上工事で建設業許可を取得するための要件
- ①経営管理業務における管理責任者を配置する
- ②専任技術者を配置する
- ③誠実性がある
- ④財産的な基礎を有している
- ⑤欠格要件に該当していない
- ⑥社会保険に加入していること
- 業務効率化で許可取得後の負担も軽減
- AnyONEとは?
- AnyONEで効率化できる業務とそのメリット
- まとめ
内装仕上工事とは
内装仕上工事とは、建築物の内部の仕上げをおこなう工事です。内装仕上工事は、建物の見栄えだけでなく、住み心地にも関わる非常に重要な工事です。
内装仕上工事と同様の意味で、内装工事という言葉が使われるケースもあります。ただ、厳密には内装工事には設備・電気工事を含みます。一方、内装仕上工事では、建物内部の仕上げのみおこなう工事を示すことが一般的です。
内装仕上工事の内容
内装仕上工事を細分化すると、以下の内容にわけられます。
●下地工事
●天井仕上工事
●壁貼り工事
●インテリア工事
●床仕上工事
●たたみ工事
●ふすま工事
●防音工事
●家具工事
特に間違いやすい工事を具体的に解説します。
下地工事では、軽量鉄骨下地(LGS)を用いて、壁や天井にボードを貼るための下地を設置していきます。特に軽量鉄骨下地が歪んでいると、ボードを張った後の仕上げも歪んでしまうため、高い精度が求められます。
内装仕上工事における防音工事とは、住宅をはじめとした一般的な建築物の防音工事です。音楽ホールなど特殊な建築物の防音工事は含まれていません。
また内装仕上工事の家具工事は、家具の組み立て、現地で家具の材料を加工して組み立てる工事を指します。
内装仕上工事の流れ
新築工事の内装仕上げ工事は、外壁や建具が設置され雨水の侵入がなくなったタイミングでおこなわれます。雨水の侵入の心配がなくなると、内装仕上げ工事の前に配線・配管工事を開始します。
配線や配管が見えていると見栄えが悪いため、ボードで隠すケースが一般的です。ただしPS・EPSなど見栄えを気にしない部屋であれば、配線に配管がむき出しとなっていることも珍しくありません。
内装仕上工事は、墨出しからおこないます。通り芯などの基準をもとに壁や天井をどこに作るのか図面をもとに目印をつけます。墨出しが狂うと、内装仕上げ全体の仕上がりがおかしくなってしまうため、失敗は許されません。
次に墨出しをもとに、下地工事とボード工事をおこないます。ボードは自立しないため、下地にビスで縫い付けて固定します。
ボード工事が終わったら仕上げに塗装をおこないます。塗装の色によって部屋の印象は大きく変わるため非常に重要な工程です。
壁と天井の塗装が終わったら最後に床の仕上げをおこないます。
内装仕上工事で建設業許可を取得する3つのメリット
内装仕上工事を請け負っている会社であっても、建設業許可を取得していないケースがあります。
ただ、内装仕上工事で建設業許可を取得すると、以下のメリットを享受できます。
①公共工事の入札に参加できる
建設業許可を取得すると、公共工事の入札に参加できます。
ただし、建築業許可を取得するだけでは、公共工事の入札に参加はできません。
経営事項審査を受け、競争入札参加資格申請をおこなえば、公共工事の入札に参加ができます。
経営事項審査を受けるためには、建設業許可が必要です。
そのため建設業許可がないと公共工事の入札への参加資格すらありません。
公共工事に参加できれば、民間工事と公共工事どちらも請け負えるため、工事料の確保ができます。また、民間工事とは異なり、工事代金の回収が確実にできることもメリットです。
②規模の大きい内装仕上工事を請け負える
建設業許可があれば、工事金額500万円を超える規模の大きい内装仕上げ工事を請け負えます。
建設業許可を受けていないと、工事金額500万円以下の規模の小さい工事しか請け負えません。
③会社の信用度が上がる
建設業許可があると、会社の信頼度が上がります。
後述しますが建設業許可を取得するためには、財務の健全性や誠実性が確認されます。
そのため建設業許可を取得できている会社は、しっかりしている会社と認識されるでしょう。
また有資格者や技術的な経験も求められるため、一定レベルの技術を有している証明も可能です。
内装仕上工事で建設業許可を取得する3つのデメリット
一方、内装仕上工事で建設業許可を取得するデメリットは以下の3つです。
①許可取得のために費用がかかる
②許可取得に手間がかかる
③取得後に維持のための手間と費用がかかる
①許可取得のために費用がかかる
建設業許可を取得するためには、費用がかかります。
- 国土交通大臣許可の手数料
- 新規の許可:15万円
- 更新および同一区分内における追加の許可:5万円
- 知事許可の手数料
- 新規の許可:9万円
- 許可の更新および同一許可区分内の追加の許可:5万円
【参考】許可申請の手続き-国土交通省
申請費用以外にも書類を取得するための費用が必要です。また、専門家に依頼する場合は、専門家に対しての報酬を支払う必要があります。
②許可取得に手間がかかる
建設業許可は申請に手間がかかります。必要書類を役所に行って集め、また一から書類作成をする必要もあります。さらに不明点があれば役所の担当者へ確認しなければなりません。
書類に不備があれば修正が必要になるため、申請するだけでも非常に手間がかかります。
③取得後に維持のための手間と費用がかかる
建設業許可を取得した後も維持のために手間と費用がかかります。建設業許可は5年に1度の更新が必要です。また更新の際には、先述したように5万円の更新料が必要です。
内装仕上工事で建設業許可を取得するための要件
内装仕上げ工事で建設業許可を取得するための要件は以下の6つです。
①経営管理業務における管理責任者を配置する
建設業許可を取得するためには、経営業務における管理責任者を配置しなければなりません。建設業の経営は他産業と異なった特徴を持っています。適切に建設業の会社を経営するためには、以下の経験を有する者が常勤の役員のうち1人はいなければいけません。
管理責任者として認められるためには、建設業の経営管理業務に管理責任者として5年以上携わっている経験が必要です。詳しくは、国土交通省のホームページをご確認ください。
②専任技術者を配置する
専任技術者の配置も建設業許可を取得するための要件です。
建設業は他産業と異なる特徴を持っており、適切に請負契約を結ぶためには、建設業についての専門知識が必要です。専任技術者は、営業所ごとに1人配置しなければなりません。
専任技術者として認められるためには、一定以上の実務経験が必要です。
また一般建設業・特定建設業どちらで許可を取得するかによって求められる実務経験は異なります。
また最終学歴によっても、必要な実務経験は変わってくるため、詳しくは国土交通省のホームページをご確認ください。
③誠実性がある
誠実性があることも建設業許可取得の要件です。
誠実性とは、請負契約の締結や履行の際に不正または不誠実の行為をおこなわないことです。
仮に不正または不誠実な行為をする恐れがある場合は、建設業許可を取得できません。
④財産的な基礎を有している
財産的な基礎、つまりある程度の資本がないと、建設業許可の取得はできません。
規模の大きな工事になるほど、資材の購入や労働者の確保などで工事代金の回収前にある程度の経費がかかります。
そのため十分な自己資本がないと、請け負った工事を進行させることはできません。一般建設業であれば、自己資金が500万円以上であるか、500万円以上の資金調達能力を有することが求められます。
特定建設業であれば、資本金の額が2,000万円以上かつ自己資本の額が4,000万以上であることが求められます。
詳しい要件は、国土交通省のホームページをご確認ください。
⑤欠格要件に該当していない
これまで解説してきた要件を満たしていても、欠格要件に該当すると建設業許可は取得できません。
許可申請書類や添付書類に虚偽の記載や重要事実の記載物があると、欠格要件として扱われる可能性があります。
詳しい欠格要件は、国土交通省のホームページをご確認ください。
⑥社会保険に加入していること
2020年(令和2年)10月に建設業法施行規則が改正され、社会保険の加入も建設業許可取得の要件となりました。
【参考】建設業法施行規則第7条2項-e-Gov法令検索
また2020年10月以前に社会保険未加入で建設業許可を取得している場合であっても、更新の時期までに社会保険に加入しないと、更新は認められません。
国土交通省は待遇改善のために、社会保険の加入を義務付けています。社会保険に加入していないと現場から締め出される可能性があるため、継続的に案件を受注していきたいと考える場合は社会保険への加入が必須です。
業務効率化で許可取得後の負担も軽減
建設業許可を取得すると、より大きな案件を受注できるようになります。
しかしその一方で、現場数の増加や管理項目の複雑化により、書類作成や原価管理にかかる手間が急激に増えるのも事実です。
特に、
- 案件ごとの見積・発注・請求書の整合性
- 現場ごとの原価の把握
- 複数現場を並行する際の進捗管理や利益率の可視化
など、手作業ではミスや抜け漏れが発生しやすくなります。
こうした許可取得後の業務をラクにできるのが、建設業向けクラウドシステムAnyONE(エニワン)です。
AnyONEとは?
AnyONEは、工務店やリフォーム会社など建設業に特化した業務効率化ツールです。見積作成から受発注、原価管理、帳票発行までを一元管理でき、現場ごとの利益をリアルタイムで可視化できます

AnyONEで効率化できる業務とそのメリット
- 帳票管理の自動化:見積書・注文書・請求書などをテンプレート化し、入力作業を大幅削減。
- 積算作業の効率化:原価データを登録しておけば、見積作成がワンクリック。担当者ごとの差も縮小。
- 原価管理の見える化:工事ごとの収支をリアルタイムで確認でき、赤字リスクを早期に察知。
- 利益率の安定化:ムダなコストや手戻りを防ぎ、許可取得後の安定経営を実現。
許可を取って終わりではなく、その後にどれだけ効率よく利益を出せるかが、今後の経営を左右します。
業務が煩雑化してきたと感じたら、まずはAnyONEの導入を検討してみてください。
まとめ
本記事では内装仕上工事の概要、内装仕上工事で建設業許可を取得するメリット・デメリット、取得のための要件について解説しました。内装仕上工事は、建物の見栄えだけでなく居住する上での快適性にも関わる重要な工事です。
内装仕上工事で規模の大きい案件を受注するためには、建設業許可が必要です。建設業許可があれば、請負金額500万円を超える案件の受注ができます。
ただ金額の大きい案件は、積算・見積り業務の負担が重くなり、原価管理の手間もかかります。そのため、規模の大きい案件を受けてもなかなか手元に利益が残らないといったケースは珍しくありません。
規模の大きい案件でも、確実に利益を残すためには、工務店・リフォーム会社に特化した業務効率化システムの導入がおすすめです。
AnyONEであれば、工務店・リフォーム会社のあらゆる業務をデジタル・クラウドの活用によって効率化します。
AnyONEの詳しい機能については、こちらの記事をご確認ください。
.png)
LinK_導入企業様の声_株式会社-Homeplus(大阪府大阪市)