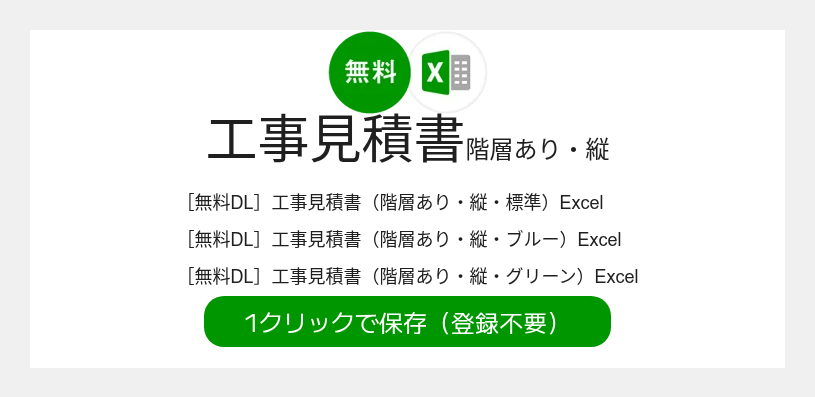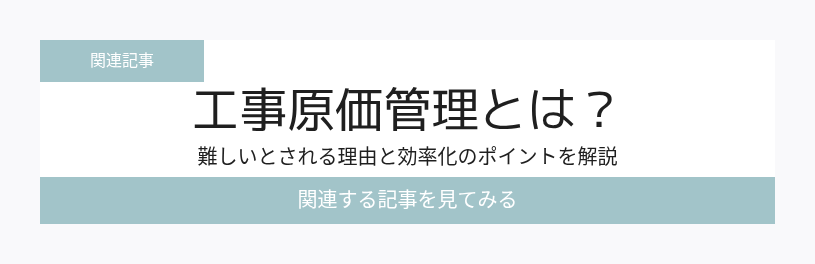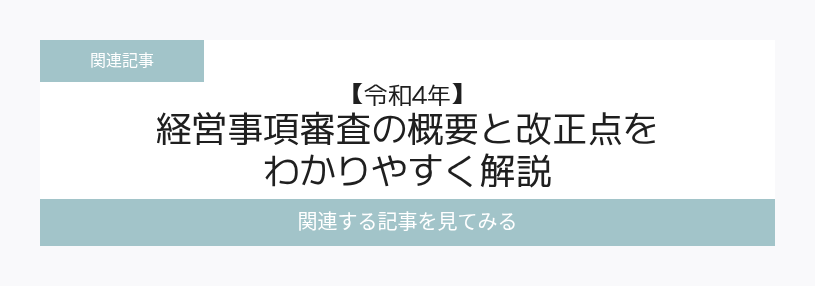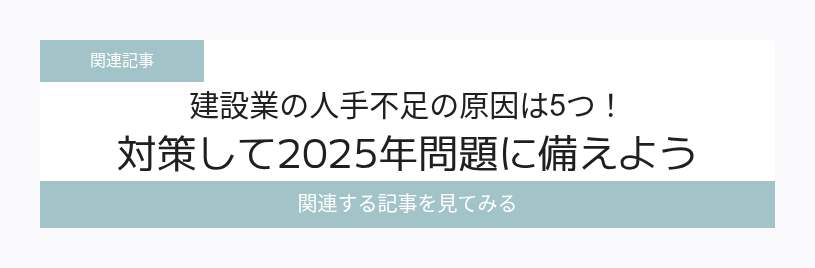基礎工事とは?工事の種類や工程、失敗しない工程表の作成について徹底解説

建設業の経理とは?仕事内容から求められるスキル、会計システムの選び方まで解説
建設現場においては、日々発生する材料費・外注費・諸経費の伝票処理が膨大であり、それぞれの費用がどの工事に紐づくかを正確に整理することは、経理担当者にとって大きな負担となります。こうした建設業の特性から、経理業務には一般的な商業簿記だけでは対応できない専門知識が求められます。
長期間にわたる工事が多数発生する建設業では、「建設業会計」という独自のルールが存在し、「完成工事高」などの特殊な勘定科目や、工事ごとの複雑な原価計算に対応する必要があります。
本記事では、建設業経理の具体的な仕事内容から、一般会計との違い、求められるスキル、キャリアアップに繋がる資格まで、その全体像を分かりやすく解説します。
INDEX
- 建設業の経理とは?
- 建設業界の特殊性から生まれた会計基準
- 一般会計と建設業会計の3つの主な相違点
- 建設業経理の具体的な仕事内容
- 日々の取引を記録する「仕訳・伝票処理」
- 工事ごとの損益を管理する「原価計算」
- 経営状況を報告する「決算業務」
- 建設業経理が抱える特有の課題
- 工事原価計算の複雑さ
- 経営事項審査への対応
- 長期にわたる工事の収益管理
- 建設業会計で使われる特殊な勘定科目
- 収益に関わる「完成工事高」
- 費用に関わる「未成工事支出金」
- その他の主要な勘定科目
- 建設業の収益計上基準「工事完成基準」と「収益認識基準」
- 完成時に一括計上する「工事完成基準」
- 進捗に応じて計上する「収益認識基準」
- 建設業の経理に求められる3つのスキル
- ①建設業会計の専門知識
- ②現場と連携するためのコミュニケーション能力
- ③業務を効率化するITリテラシー
- 建設業経理のキャリアアップに繋がる「建設業経理士」
- 建設業経理士とはどんな資格か
- 資格取得が経営事項審査で有利になる理由
- 複雑な会計業務を効率化するシステムの導入
- システムが解決する課題
- 自社に合ったシステムの選び方
- 建設業経理の業務効率化に役立つシステム「AnyONE」
- 現場と事務の情報連携がスムーズ
- 操作性と業務負担の軽減
- 補助金・法改正への対応も安心
- まとめ
建設業の経理とは?
建設業の経理は、一般的な商業簿記の知識だけでは対応が難しい、専門的な業務分野です。
建設工事は着工から完成までが長期にわたることが多く、会計期間をまたぐことも珍しくありません。
このような業界の特性に合わせて設けられた独自の会計ルールが「建設業会計」です。たとえ他業種での経理経験が豊富なベテランであっても、この特殊な会計処理に戸惑うことがあります。
建設業界の特殊性から生まれた会計基準
建設業会計が特別とされる理由は、主に次の2点です。

このため、一般会計とは異なる勘定科目や収益計上基準が定められています。
一般会計と建設業会計の3つの主な相違点
建設業会計を理解する鍵は、一般会計との違いを明確に把握することです。
大きな違いは主に以下の3点に集約されます。
- 特殊な勘定科目 : 「売上」を「完成工事高」と呼ぶなど、建設業の実態に合わせた独自の勘定科目が使用されます。
- 工事ごとの原価計算 : 製品ごとではなく、工事現場一つひとつを単位として原価を計算します。
- 独自の収益計上基準 : 工事期間が会計年度をまたぐケースに対応するため、収益を計上するタイミングに特別な基準が設けられています。
これらの違いを一つずつ理解していくことが、建設業経理マスターへの近道です。
建設業経理の具体的な仕事内容
建設業経理の業務は多岐にわたりますが、中心となるのは「仕訳・伝票処理」「原価計算」「決算業務」の3つです。
どれも会社の健全な経営を支える重要な業務です。
日々の取引を記録する「仕訳・伝票処理」
日々の業務の基本は、発生した取引を正確に帳簿に記録することです。材料の仕入れ、外注費の支払い、現場の経費精算など、お金の動きをすべて勘定科目に分類し、仕訳を行います。
建設業では、これらの費用が「どの工事に関するものか」を明確に紐づけて管理する必要があります。
工事ごとの損益を管理する「原価計算」
建設業経理の主要な業務が、工事ごとの原価計算です。
一つの工事にかかる材料費、労務費、外注費、経費を正確に集計し、その工事が黒字なのか赤字なのかをリアルタイムで把握します。
この原価管理の精度が、会社の利益に直結するため、重要な業務となります。
精緻な原価管理は、次の工事の見積もり精度を高める上でも不可欠です。
経営状況を報告する「決算業務」
年に一度の決算業務では、一年間の取引を集計し、財務諸表(貸借対照表、損益計算書など)を作成します。建設業では、これらの書類に加えて「完成工事原価報告書」という独自の報告書も必要です。
これは、その期に完成した工事の原価の内訳を示すもので、建設業法で提出が義務付けられています。 期末時点で進行中の工事の会計処理も複雑であり、年次決算は経理担当者の専門性が最も発揮される場面です。
| 業務内容 | 主な役割 | 特徴 |
| 仕訳・伝票処理 | 日々の取引を帳簿に記録 | ・材料費、外注費、経費などを勘定科目に分類
・どの工事に関する費用かを明確に紐づける必要あり ・一般経理よりも複雑 |
| 原価計算 | 工事ごとの損益を管理 | ・材料費、労務費、外注費、経費を正確に集計
・黒字/赤字をリアルタイムで把握 ・利益や次回見積り精度に直結する重要業務 |
| 決算業務 | 経営状況を財務諸表で報告 | ・貸借対照表・損益計算書を作成
・建設業特有の「完成工事原価報告書」の提出が必要 ・進行中工事の処理が複雑で専門性が求められる |
建設業経理が抱える特有の課題
建設業の経理業務は専門性が高く、他業種にはない独自の課題を抱えています。
その仕組みを理解し、効率化の方法を見つけることが、日々の業務改善につながります。
工事原価計算の複雑さ
前述の通り、工事ごとの原価計算は建設業経理の要ですが、その計算は複雑です。
特に、複数の工事現場で共通して使用する機械の費用や人件費を、どのように各工事に配分するかといった判断には専門的な知識と経験が求められます。
手作業での集計はミスが発生しやすく、多くの経理担当者が頭を悩ませるポイントです。
経営事項審査への対応
公共工事の入札に参加するためには、経営事項審査(経審)を受ける必要があります。これは、企業の経営状況や技術力などを客観的に評価する制度で、評価点が高いほど入札で有利になります。
この審査では、財務諸表の内容が厳しくチェックされます。
日頃から法令に準拠した会計処理を行うことが、経理担当者の重要な役割です。
長期にわたる工事の収益管理
工期が数年に及ぶ大規模プロジェクトでは、収益をどのタイミングで計上するかが経営成績に大きな影響を与えます。
資材価格の変動や予期せぬトラブルによる追加コストなど、長期化すればするほど不確定要素が増え、見積もりと実績の間に差異が生じやすくなります。
こうした資材費の変動や追加コストなどリスク管理も重要です。
建設業会計で使われる特殊な勘定科目
建設業会計を学ぶ上で、まず押さえるべきは特有の勘定科目です。
ここでは代表的なものを紹介します。
収益に関わる「完成工事高」
「完成工事高(かんせいこうじだか)」は、一般会計の「売上高」に相当します。工事が完成し、顧客に引き渡された時点で計上される収益です。
これに対応する未回収の代金は、「完成工事未収入金(かんせいこうじみしゅうにゅうきん)」とされ、一般会計の「売掛金」にあたります。
費用に関わる「未成工事支出金」
「未成工事支出金(みせいこうじししゅつきん)」は、一般会計の「仕掛品」に相当する科目で、資産に分類されます。
決算時点でまだ完成していない工事のために支出した材料費や労務費などを計上します。これが完成した時点で、「完成工事原価」という費用科目に振り替えられます。
その他の主要な勘定科目
その他にも、建設業会計では以下のような特有の勘定科目が使われます。
これらを正しく使い分けることが、正確な財務諸表作成の第一歩です。
| 建設業会計の勘定科目 | 対応する一般会計の勘定科目 | 概要 |
| 工事未払金 | 買掛金 | 材料費や外注費などの未払い額 |
| 未成工事受入金 | 前受金 | 工事の完成前に受け取った内金など |
| 完成工事原価 | 売上原価 | 完成した工事にかかったすべての費用 |
建設業の収益計上基準「工事完成基準」と「収益認識基準」
建設業会計において最も重要な論点の一つが、収益をいつ計上するかという基準です。現在は主に2つの基準が用いられています。
| 基準 | 収益計上のタイミング | メリット | デメリット |
| 工事完成基準 | 工事が完成し顧客に引き渡した時点 | ・処理がシンプルで分かりやすい | ・工期が長いと完成まで売上ゼロ ・期間中の経営実態が財務諸表に反映されにくい |
| 収益認識基準 | 工事の進捗度合いに応じて計上 | ・進捗に応じて収益を認識できる ・長期工事でも各期の業績を適切に反映可能 |
・進捗度を合理的に見積もる必要があり処理が複雑 |
完成時に一括計上する「工事完成基準」
「工事完成基準」は、工事が完成し、目的物を顧客に引き渡した時点で収益と原価をまとめて計上する方法です。
処理がシンプルで分かりやすい反面、工期が長い場合は完成まで売上がゼロとなり、期間中の経営実態が財務諸表に反映されにくいというデメリットがあります。
進捗に応じて計上する「収益認識基準」
「収益認識基準」は、より新しい会計基準で、工事の進捗度合いに応じて収益を認識(計上)していく考え方です。決算期末の時点で工事の進捗度を合理的に見積もり、その割合に応じて収益と原価を計上します。これにより、長期工事であっても各会計期間の業績をより適切に反映させることが可能になります。
建設業の経理に求められる3つのスキル
建設業の経理担当者として活躍するためには、会計知識以外にもいくつかの重要なスキルが求められます。

①建設業会計の専門知識
当然ながら、これまで解説してきた建設業会計に関する深い知識は必須です。
特有の勘定科目、原価計算、収益認識基準などを正しく理解し、実務で応用できる能力が求められます。
知っているかどうかで、仕事の進めやすさも評価も大きく変わります。
②現場と連携するためのコミュニケーション能力
経理はデスクワークだけではありません。工事原価を正確に計算するためには、工事現場の担当者と密に連携し、材料の使用状況や作業員の稼働状況といった情報を正確に入手する必要があります。
現場の状況を理解し、円滑な人間関係を築くコミュニケーション能力は、経理担当者にとって意外なほど重要なスキルです。
③業務を効率化するITリテラシー
現代の経理業務において、会計ソフトやExcelなどのITツールを使いこなす能力は不可欠です。特に建設業会計は複雑なため、会計システムを導入して業務を自動化・効率化する企業が増えています。
新しいシステムに適応し、その機能を最大限に活用するITリテラシーは、自身の業務負担を軽減し、より付加価値の高い仕事に取り組むために重要となります。
建設業経理のキャリアアップに繋がる「建設業経理士」
建設業経理のプロフェッショナルとしてキャリアを築く上で、有効な資格が「建設業経理士」です。
建設業経理士とはどんな資格か
建設業経理士は、一般財団法人建設業振興基金が実施する検定試験で、建設業会計に特化した知識とスキルを証明する唯一の専門資格です。実務レベルとされる2級以上を取得すると、専門性を客観的にアピールでき、就職や転職、社内での評価向上に繋がります。
資格取得が経営事項審査で有利になる理由
この資格が特に重要視される理由は、公共工事の入札に参加する企業が受ける「経営事項審査」にあります。この審査では、企業の評価項目の中に「公認会計士等数」と「経理処理の適正を確認できる者(2級以上の建設業経理士など)の数」があり、有資格者がいると企業の評価点が加算される仕組みになっています。
このため、企業は資格取得者を積極的に採用・奨励しており、資格を持つ人材は業界で高く評価されます。
複雑な会計業務を効率化するシステムの導入
人手不足が深刻化する中、複雑で属人化しがちな建設業の経理業務を効率化するために、建設業界のお金の流れに対応したシステムの導入が最適な解決策となります。
システムが解決する課題
建設業向けのシステムは、特有の勘定科目に標準で対応しているほか、煩雑な工事ごとの原価管理や進捗管理を自動化する機能を備えています。
これにより、手作業によるミスを削減し、経理担当者の負担を大幅に軽減することができます。
また、経営陣はリアルタイムでいつでも数字が見えて、次の判断がしやすくなります。
自社に合ったシステムの選び方
会計システムを選ぶ際は、自社の規模や業務フローに合っているかを確認することが重要です。クラウド型かオンプレミス型か、インボイス制度や電子帳簿保存法といった法改正にきちんと対応しているか、サポート体制は充実しているか、といった点を比較検討しましょう。多くのシステムが無料トライアルを提供しているため、実際に操作感を試してから導入を決定することをおすすめします。
建設業経理の業務効率化に役立つシステム「AnyONE」
複雑な工事ごとの原価管理や進捗管理、伝票処理など、建設業の経理業務はどうしても手間がかかります。
こうした課題を解決するために、多くの企業が建設業向けのシステム「AnyONE」を導入しています。
現場と経理をつなぐ仕組みを整えることで、経理担当者の業務効率はもちろん、会社全体の利益管理も精度が高まります。
現場と事務の情報連携がスムーズ
AnyONEでは、作成した見積や発注状況など、お金の流れをリアルタイムで共有できます。これにより、どの費用がどの工事に紐づくのかを簡単に整理でき、手作業による集計ミスを大幅に削減できます。
操作性と業務負担の軽減
経理担当者が直感的に操作できるUI設計で、複雑な原価計算や仕訳作業も効率的に進められます。初めて建設業会計を扱う方でも、スムーズに業務をスタートできるのが嬉しいポイントです。
補助金・法改正への対応も安心
AnyONEは、電子帳簿保存法やインボイス制度などの最新法規制にも対応しています。また、補助金申請に必要な書類の出力や集計も簡単に行えるため、経理業務の負担をさらに軽減できます。
まとめ
建設業の経理は、一般会計とは異なる複雑さと専門性が求められる仕事ですが、それだけに大きなやりがいと安定したキャリアに繋がる魅力的な職種です。
本記事で紹介した業務内容やスキル、システムの活用を意識することで、建設業経理のプロを目指すことができます。
また、建設業の経理業務をさらに効率化し、プロとしてのキャリアを加速させたい方には
システムの導入を成功させるためのポイントをまとめた、お役立ち資料を無料で進呈しております。日々の業務改善のヒントとして、ぜひご活用ください。