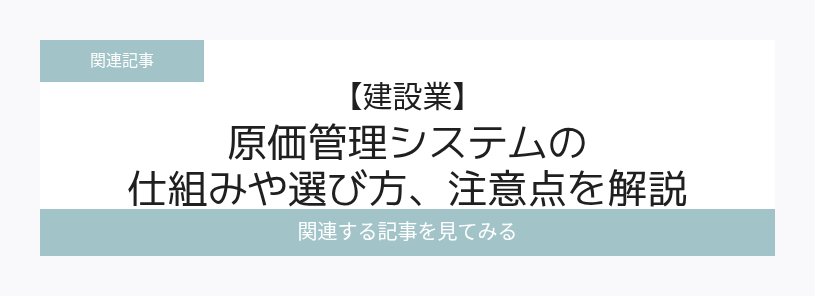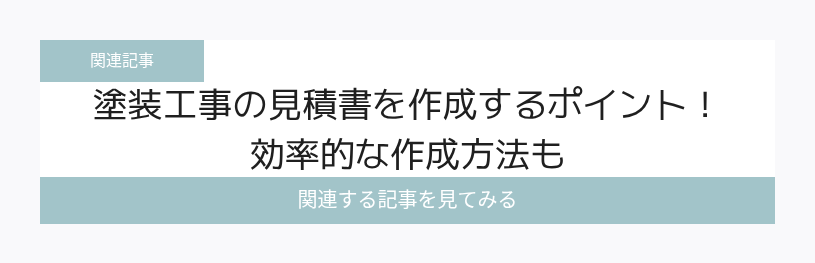建設業の経理とは?仕事内容から求められるスキル、会計システムの選び方まで解説

外壁塗装の原価率は60%以上?内訳・利益改善のポイント
外壁塗装は住宅の耐久性を守る重要な工事ですが、工務店にとっては「思ったより利益が残らない」業務のひとつでもあります。その背景には原価率の高さがあります。
一般的に外壁塗装の原価率は60%〜70%、粗利率は35〜40%が目安です。
本記事では、外壁塗装の原価構成と計算の考え方、業界平均の利益率、利益を圧迫する要因、改善のポイントをわかりやすく解説します。
INDEX
- 外壁塗装の原価率は60%以上
- 外壁塗装の原価率内訳
- 職人の人件費(目安30〜45%)
- 塗料などの材料費(目安20%)
- 足場工事費(目安10〜15%)
- 営業・会社経費(目安10〜20%)
- 外壁塗装で利益率が低くなる要因
- 下請けの仕事を多く受注している
- 過度な値下げをしている
- 営業職や職人の雇いすぎ
- 材料費の高騰など外的要因
- 外壁塗装で利益を確保する6つのポイント
- 1. 元請けの仕事を増やす
- 2. 販売単価を上げる
- 3. 自社で職人を育成する
- 4. 材料価格の交渉をする
- 5. 過剰在庫をなくす
- 6. 広告・宣伝費用を見直す
- AnyONEで外壁塗装の原価率を最適化して利益率UP!
- 外壁塗装の原価についてよくある質問
- Q1. 塗装屋は儲かりますか?
- Q2. 塗装の1人工の単価はいくらですか?
- まとめ
外壁塗装の原価率は60%以上
外壁塗装工事の原価率は、一般的に60〜70%程度が目安とされています。
ただし、この比率は会社の体制や工事の仕組みによって変動します。たとえば足場を自社保有していれば原価率は下がりますし、外注比率が高い会社では逆に上がる傾向です。
大切なのは「自社の原価率を正しく把握すること」と「どこに改善余地があるかを見抜くこと」です。
外壁塗装の原価率内訳
外壁塗装の原価は大きく以下の4つに分けられます。
- 1.職人の人件費(目安30〜45%)
- 2.塗料などの材料費(目安20%)
- 3.足場工事費(目安10〜15%)
- 4.営業・会社経費(目安10〜20%)
職人の人件費(目安30〜45%)
最も大きな割合を占めるのが人件費です。1人工(にんく)あたりの相場は地方で15,000〜20,000円、都市部では20,000〜25,000円ほど。
外注職人に依存すれば、人工単価はさらに上がります。
工期が1日延びるだけでも数万円単位でコストが膨らむため、予定人工と実績人工の差異を管理することが利益確保のカギです。
塗料などの材料費(目安20%)
塗料・シーリング材・下地処理材といった材料費は全体の約20%を占めます。高耐久塗料を採用すれば、比率はさらに上がるでしょう。
材料費は「数量の見積もり」と「仕入れ単価」で決まります。
見積もりを甘くすれば余剰在庫が生まれ、単価交渉を怠れば無駄な支出が発生します。
現場単位で必要量を精緻に見積もること、主要銘柄を絞って単価交渉を進めることが、材料費コントロールの基本です。
足場工事費(目安10〜15%)
外壁塗装に欠かせない足場工事費は全体の10〜15%程度を占めます。
外注業者に依頼するケースが多く、㎡単価は700〜1,100円程度。
複数の現場をまとめて発注したり、屋根塗装や雨樋交換を同時に提案して「足場を共用」したりすれば、施主の負担を軽減しつつ、自社の利益率も改善できます。
営業・会社経費(目安10〜20%)
広告宣伝費や営業人件費、現場管理費、会社の固定費などが含まれます。
広告費は売上の5〜10%以内に抑えるのが理想。口コミや既存施主からの紹介を増やし、広告依存度を下げる仕組みが必要です。
外壁塗装で利益率が低くなる要因
外壁塗装は原価率が高いため、少しの要因でも利益が大きく削られます。
代表的な要因を4つ見てみましょう。

下請けの仕事を多く受注している
下請け主体で仕事を回していると、元請けに20〜30%のマージンを取られ、粗利が大きく削られます。
さらに仕様や工程の決定権も元請けにあるため、現場の工夫で単価を上げる余地も限られます。結果として「頑張っても利益が残りにくい構造」になってしまいます。
過度な値下げをしている
適正価格で積算した見積の値引き余地は最大でも10%程度です。これ以上の値引きは粗利を圧迫し、品質や工程にしわ寄せが発生します。
値引きで受注を狙うより、耐久性・保証・付帯工事などの付加価値を訴求して価格ではなく価値で選ばれる受注を目指しましょう。
営業職や職人の雇いすぎ
人員を抱えすぎると、受注が落ち込んだ際に固定費が一気に経営を圧迫します。職人の場合も、工程管理が甘ければ待機時間などが増え、実質的な人工単価が高くなります。稼働率を見える化し、適正な人員配置を維持することが重要です。
材料費の高騰など外的要因
近年は原油価格や物流費の高騰により、塗料単価が上昇傾向にあります。このような外的要因は避けられませんが、契約に「見積有効期限」や「再見積条項」を設けたり、仕入れ先との年間契約や複数調達ルートを確保したりして、影響を最小限に抑えましょう。
外壁塗装で利益を確保する6つのポイント
外壁塗装で利益を守るには、日々の工事運営に直結する施策が欠かせません。
ここでは特に効果の大きい6つの方法を紹介します。
1. 元請けの仕事を増やす
直販比率を高めることは最も効果的な利益改善策です。地域事例の発信や既存施主からの紹介制度を整え、自社で直接契約を獲得できる仕組みを育てましょう。
2. 販売単価を上げる
「品質・保証・高耐久塗料」といった付加価値を丁寧に説明し、安さではなく安心感や長期的コストパフォーマンスで選んでもらう工夫が必要です。たとえば、三段階見積(スタンダード・高耐久・プレミアム)で比較させると、真ん中のプランが選ばれやすくなります。
3. 自社で職人を育成する
外注依存を減らし、自社で職人を育成すれば、人工単価を抑えつつ品質を安定させられます。教育コストはかかりますが、長期的には利益構造を改善する投資になります。
4. 材料価格の交渉をする
主要銘柄を絞り、仕入れ先と継続的に交渉することで、単価を抑えることができます。また、共同購入や年間契約も有効です。
5. 過剰在庫をなくす
必要以上に在庫を抱えてしまうと使い切れないまま劣化したり、色や仕様が合わずに再利用できなくなったりして、最終的に廃棄コストが発生します。
これは工務店にとって「見えない損失」となり、利益をじわじわと削っていきます。
在庫を適正化するには、現場ごとに必要量を正確に見積もることが第一歩です。さらに、各現場から余った塗料を戻し入れるルールを徹底することで、使い回せる在庫を確保しつつ、無駄な発注を減らせます。定期的に棚卸しをおこない「残っているが使えない在庫」を洗い出す仕組みを持つことも重要です。
6. 広告・宣伝費用を見直す
広告費については、売上に対する比率を常に管理し、効果の低い媒体は見直しましょう。
また、口コミやWeb集客を強化し、広告依存を減らすことで利益率を改善できます。
AnyONEで外壁塗装の原価率を最適化して利益率UP!
ここまで紹介した改善策を実行するには、数字を感覚で追うだけでなく、案件ごとの原価や利益をリアルタイムに把握できる仕組みが必要です。
人件費や材料費、足場費といった要素は案件ごとに変動するため、手作業での集計ではどうしても遅れや抜け漏れが生じてしまうもの。
そこで役立つのが、工務店向けの業務効率化システム『AnyONE』です。
『AnyONE』なら、見積から実行予算、発注、支払い、請求までを一元管理し、案件ごとの利益率を即座に可視化。
数字を「勘」ではなく「データ」で管理できるようになり、利益を守るための意思決定がスムーズになります。
外壁塗装の原価についてよくある質問
「塗装業は本当に儲かるのか」「職人の人工単価はいくらが相場なのか」といった基本的な疑問は、利益構造を理解するうえで避けて通れません。
ここでは、工務店経営に直結する代表的な質問を取り上げ、わかりやすく解説します。
Q1. 塗装屋は儲かりますか?
原価を正しく管理し、直販比率を高めて広告依存を減らせば十分に儲かります。
営業利益率で8〜10%を目指すことも可能です。逆に、下請け依存や値下げ競争に陥ると、どれだけ施工件数を増やしても利益は残りません。
Q2. 塗装の1人工の単価はいくらですか?
地域やスキルによりますが、地方では15,000〜20,000円、都市部では20,000〜25,000円が相場です。
工期や現場条件によって増減するため、見積時に細かく算出することが大切です。
まとめ
外壁塗装は需要が安定している反面、原価率が60〜70%と高く、利益が残りにくい工種です。
職人の人件費や材料費、足場費や営業経費が大きな割合を占め、下請け依存や値下げ、人員配置の偏り、材料費高騰などで利益率はさらに低下します。
とはいえ、元請け比率の向上や単価の適正化、自社職人の育成、仕入れ・在庫・広告費の見直しといった基本的な取り組みを積み重ねれば改善は可能です。
そのために欠かせないのが、原価や利益をリアルタイムで把握できる仕組みづくりです。感覚ではなくデータで管理することで、利益を守りながらスピーディな意思決定を目指せるでしょう!
記事監修:大﨑 志洸/株式会社Limited 取締役
兵庫県出身。施工実績は累計5,000件以上。
総工費10億円規模のプロジェクトに従事し、施工管理の実務経験を積む。
その後、商社の建設事業部にて総工費3億円規模のビル改修やオフィス・店舗内装を手掛け、同事業部の立ち上げを主導。
現在は、2024年2月に株式会社Limitedを代表の吉田と共同設立し、内装工事の受注に加え、施工管理の派遣・人材紹介業務に関するコンサルティング事業を展開している。