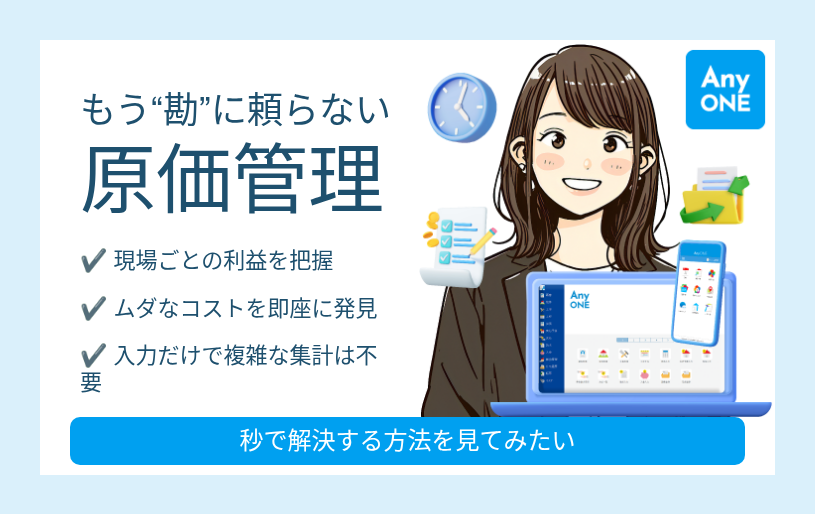【塗装工事】請求書の作り方・書き方|インボイス対応・人工費の計算方法・作成手順を解説

活動基準原価計算(ABC)とは?計算方法や事例を解説!
原価がなぜ思ったように合わないのか、悩んでいませんか?
そのような時に役立つのが、活動基準原価計算(ABC)です。活動基準原価計算(ABC)は、間接費を活動単位で細分化し、実態に即した原価を明らかにします。
本記事では、ABCの基本から導入効果、計算方法、注意点までをやさしく解説。より正確なコスト把握を通じて、経営改善のヒントをお届けします。
INDEX
活動基準原価計算(ABC)とは何か?
ABC(活動基準原価計算)は、間接費を「活動」に分解してコストを正確に把握する手法です。従来の原価計算では見えにくかった実態に迫るため、経営判断の精度を高めたい場合に有効です。
原価計算との違い
従来の原価計算では、共通費や現場間接費などの間接費を労務費や材料費といった直接費に基づいて一括配賦するため、実際の工事や作業内容と関係の薄いコストまで各工事原価に含まれてしまうという課題がありました。
一方でABCでは、建設現場で行われる各種活動―例えば、安全管理、現場巡回、資材搬入、機械設置など―を単位として間接費を細分化し、それぞれの活動に実際どれだけのコストがかかっているかを正確に把握します。これにより、各現場や工程にかかるコストを明確化し、個々の建設プロジェクトに対する正確な原価配分が可能となります。
活動基準原価計算(ABC)の計算方法
活動基準原価計算(ABC)を建設業で導入する際の計算ステップは、主に次の3段階で行われます。
ステップ①現場監督業務や安全管理、重機運搬、資材搬入といった各「活動」に対して、共通の間接費を割り当てます。
ステップ②各活動にかかるコストを把握するため、「活動あたりの単価(例:1時間あたりの費用)」を算出します。
ステップ③各現場や工事ごとにその活動がどれだけ実施されたか(=コストドライバー)を測定し、その量に単価を掛けて原価を計算します。
具体的な計算式は以下の通りです。
- ●工事原価 = 活動単価 × コストドライバー量
たとえば、「現場管理」活動の総コストが60万円で、月間の総管理時間が240時間だった場合、管理活動の単価は2,500円/時間になります。あるA現場の管理に80時間かかった場合、その現場にかかる現場管理費は20万円(2,500円×80時間)と計算できます。
ABCとABM(活動基準原価管理)の違い
ABC(活動基準原価計算)とABM(活動基準原価管理)は密接に関連した考え方ですが、それぞれ異なる目的を持っています。
建設業において、ABCは現場監督、工程管理、安全パトロール、資材搬入といった建設活動に関わる共通費(間接費)を、各工事案件や工程に対して合理的に配分することを目的としています。
一方、ABMは、これらの活動を単に「配分」するだけでなく、「管理・最適化」することに主眼を置いています。具体的には、建設現場で行われるさまざまな活動を「付加価値活動」(例:構造物の施工、設計調整など)と「非付加価値活動」(例:不要な待機時間、二重確認作業など)に分類し、非付加価値活動の削減を通じて間接費そのものの削減を図ります。
ただし、単に活動量を減らすだけでは、必ずしも間接費が比例して削減されるわけではありません。たとえば、現場巡回の回数を減らしても、安全対策に必要な基本コストは一定であるため、削減には注意と計画が必要です。
活動基準原価計算(ABC)のメリット
ABCを導入することで、原価の正確な把握や価格設定の見直し、非効率な活動の発見など、多くの経営メリットが得られます。
正確に原価計算を行える
活動基準原価計算(ABC)を導入することで、企業は原価をより正確に把握できるようになります。
また、工務店が取り扱う様々な工事種別(新築、リフォーム、修繕など)ごとに必要な作業工程が異なりますが、ABCによって各工程の原価を正確に計算できるため、工事種別ごとの収益性分析も可能になりました。
このような正確な原価計算により、見積もりの精度が向上し、適正な価格設定が可能になるだけでなく、工事の進行に合わせたリアルタイムでのコスト管理も実現できます。
適切な価格設定を判断しやすい
活動基準原価計算(ABC)を導入することで、企業は適切な価格設定を判断しやすくなります。ABCによって製品やプロジェクトの原価をより正確に把握できるため、適正な利益率を確保した価格設定が可能になるのです。
無駄な活動を把握できる
活動基準原価計算(ABC)のメリットとして特筆すべきは、無駄な活動を明確に把握できる点です。ABCでは各活動にかかるコストを詳細に算出するため、どの工程でコストが過剰になっているかを容易に特定できます。
ABCのデータを分析することで、コスト削減の余地がある活動を見極めることができ、より効率的な経営判断につながります。
活動原価計算(ABC)のデメリット
高精度な原価計算が可能なABCですが、データ収集の手間や導入コストなどの課題も存在します。導入前に理解しておくことが重要です。
現場からデータを集める手間がかかる
活動基準原価計算(ABC)を導入する際の大きな課題として、現場からのデータ収集の手間が挙げられます。ABCは活動ごとに細かくコストを把握する必要があるため、現場ごとの作業時間、使用した重機の稼働時間、作業員の人数、使用資材の数量などを詳細に記録しなければなりません。
この作業は日々の業務に加えて行うことになるため、現場の従業員に大きな負担をかけることになります。特に多くの活動を行う製造業や建設業では、活動ごとのデータ収集が膨大な作業量となることも少なくありません。
ぴったり正確な原価は算出できない
活動基準原価計算(ABC)は理論上優れた手法ですが、完璧な原価算出は実際には難しいという現実があります。なぜなら、すべての活動を細分化して完全に把握することは、実務上極めて困難だからです。
このような課題があるものの、従来の原価計算よりは正確性が高いため、経営判断の材料として十分に価値があります。完璧を求めるよりも、継続的な改善と実用性のバランスを取ることが重要でしょう。
システム導入が前提になることもある
活動基準原価計算(ABC)の実践には、専用のシステム導入が不可欠なケースが多いです。膨大な活動データの収集・分析・配賦計算を手作業で行うのは現実的ではないからです。特に大企業や複雑な製造工程を持つ企業では、ERPシステムやABC専用ソフトウェアの導入が前提条件となることがあります。
こうしたシステムは初期投資が高額になりがちで、導入コストと運用コストの両面で経営判断が必要です。特に中小企業にとっては大きな負担となる可能性があります。
とはいえ、適切なシステム選定ができれば、正確な原価計算とデータ分析による経営改善のメリットは大きいでしょう。
工事の原価管理を効率化するならAnyONE
工務店での原価管理を効率化したいなら、工務店向け業務効率化システムAnyONEがおすすめです。建設業における原価管理は、現場ごとに条件が異なるため非常に煩雑になりがちです。AnyONEを導入すれば、見積もり・実行予算・発注といった各段階での利益の推移を、案件ごとに一元管理することが可能です。
まとめ
活動基準原価計算(ABC)は、間接費を「活動」単位で細かく把握・配賦することで、従来の原価計算では見えなかった実際のコスト構造を明らかにする手法です。正確な原価把握や適正な価格設定、非効率な活動の特定といった多くのメリットがある一方、導入にはデータ収集やシステム整備などの負担もあります。自社の業種や規模に応じて導入の可否を検討し、経営判断の質向上に役立てましょう。