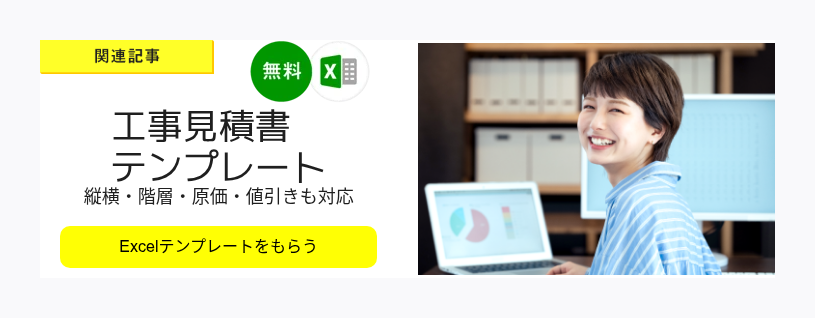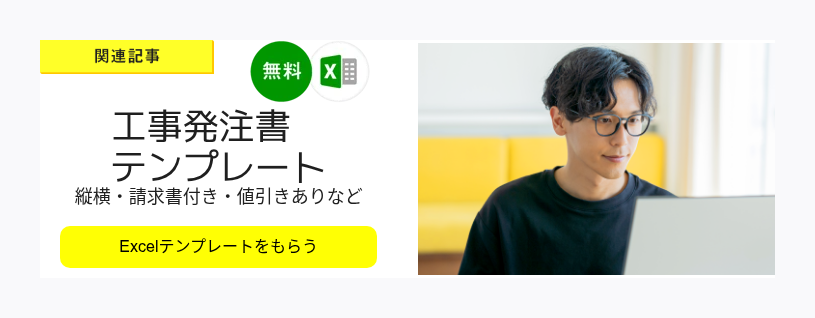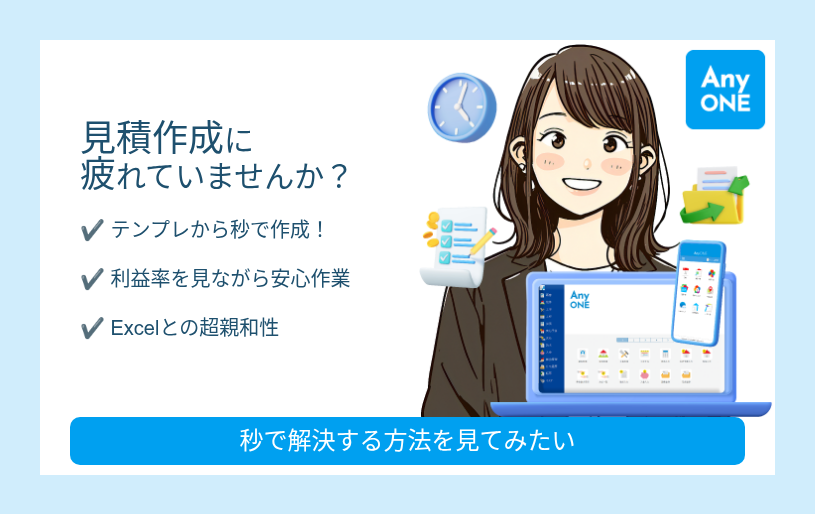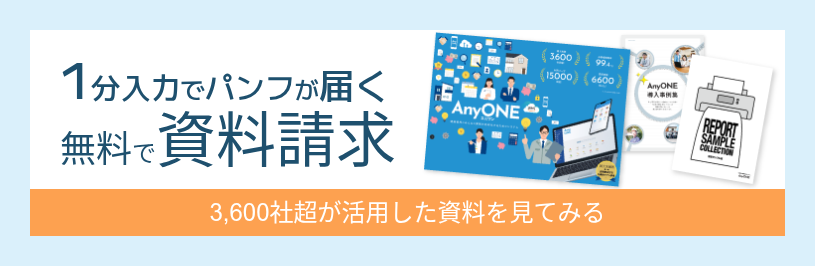【建設業】請求書の正しい作り方と書き方|必須項目・テンプレート・送付方法まで解説

見積書に法的効力はある?見積書が必要な4つの理由も解説
見積書は契約締結前に発行される書類です。「見積書の発行に法的拘束力があるのか」と、疑問を持っている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、見積書の法的拘束力や見積書が必要な理由、見積書の有効期限について解説します。見積書の法的拘束力について詳しく知りたい方は、ご一読ください。
INDEX
見積書に法的効力はある?
民法上では、見積書の発行は法的に義務付けられていません。見積書は受注前に発行される書類のため、見積書はあくまで商慣習によって発行されています。
ただし建設業は、建設業法第20条によって見積書の発行が義務付けられているため注意しましょう。見積書の提出は、請負契約が成立するまでに交付しなければならないと定められています。
また建設業法では、見積書に下記を明らかにしなければならないとも定められています。
- 工事種別ごとの材料費
- 労務費その他の経費の内訳
- 工事の工程ごとの作業
- 作業の準備に必要な日数
見積書なしで発注は可能?
先述したように建設業界は建設業法によって、見積書の発行が義務付けられています。仮に見積書の発行に法的義務がない場合であっても、トラブル防止の観点から見積書は発行しましょう。
仮に口頭だけで契約を結んでしまうと、契約締結後に発注者から以下の要求を受けたときの対抗手段がなく、要求をそのまま受け入れざるを得なくなります。
- 発注者都合による価格の引き下げ
- 請負工事範囲の拡大
- 納期の短縮
発注者から無茶な要求を受けた場合は、契約の元になった見積書が対抗手段となります。見積書に記載した金額や見積条件が、取引先とのトラブルから自社を守ることになるため、見積書は必ず書面で残しておきましょう。
見積書の押印は法的効力に影響しない?
工事見積書に押印して発行するケースは多いですが、実は押印なしでも問題はありません。押印する企業が多い理由は見積書がずさんなものではなく、十分に協議したうえでの見積であると証明するためです。見積書は施主の社内稟議で決済されますが、その際に押印があった方が会社的な信用を演出できます。
押印なしでも見積書の発行は可能ですが、会社としての信頼感を高めるという意味でも角印を捺印しての提出をおすすめします。
PDFの見積書も法的効力はある?
仮に見積書をPDFで発行した場合でも、法的効力に影響はありません。そもそも見積書に発行様式の規定はなく、どのような形で発行しても問題ないとされています。しかし、建設業では従来、書類で重要な情報を証拠として残す慣習があるため、見積書も慣習的に紙で発行されてきました。
近年は電子契約システムを取り入れる事業者も増加しており、PDFにて見積書発行を求められるケースもあるでしょう。その場合はPDFにて見積書を発行し、施主へ電子メールなどで確認してもらってください。
見積書が必要な4つの理由
見積書が必要な理由は下記の4つです。
- 発注者との認識のズレをなくす
- 取引の客観的な証拠
- 取引の流れが明確になる
- 支払い条件が明確になる
見積書にはトラブルから自社を守れる以外にも必要な理由があります。普段から口頭で契約をしている方は、参考にしてください。
見積書の詳しい書き方・作成方法については詳しく解説している記事をご確認ください。
発注者との認識のズレをなくす
見積書があると下記の項目が明確になり、発注者との認識のズレをなくせます。
- 金額
- 納期
- 作業範囲
- 有効期限
上記の項目が明確だと、発注者とのトラブルを未然に防げます。また見積書に有効期限が記載してあれば、発注者の購買意欲を促進して早期の発注を促すことも可能です。
さらにしっかりと見積条件を記載していれば、価格変動リスクにも対応できます。昨今は急激な円安、ウクライナ侵攻の影響によって原材料価格が上昇しました。
原材料価格の増加分を価格転嫁できないと、工事原価が増加してしまい利益を圧迫する原因となります。「受注者の責めによらない事情によって工事原価が上昇した場合は、取引価格の再度協議をおこなう」といった文言を見積条件して記載しておけば、価格変動リスクに対応が可能です。
取引の客観的な証拠
見積書があれば取引の内容を記録できるため、客観的な証拠となります。
見積書があれば取引の内容を記録できます。取引の記録内容があれば、発注者から無茶な要求を受けるといったトラブルを防止できます。
仮に見積書がなく取引を開始すると、発注者から以下のような無茶な要求をされても断りにくいです。
- 契約締結後の値下げ交渉
- 作業範囲の拡大
- 一方的な納期の短縮
先述したように見積書は、不当な要求から自社を守るための対抗手段となるため、口頭での契約は避け必ず見積書を発行しましょう。
取引の流れが明確になる
一般的な取引では、見積書が起点になるケースが多いです。
見積書があると取引は、以下のような流れで進みます。
1.発注者が見積依頼書を発行する
2.受注者が見積書を発行する
3.発注者が見積書を確認して工事請負契約書・発注書を発行する
4.受注者が工事請負契約書・発注書を確認して、発注請書を発行する
上記の流れで取引が進むと、取引内容が書面で残るため取引の流れが明確になります。「いつも口頭で契約が進んでしまい、案件の内容を正確に把握できていない」と悩む方は、見積書を作成して取引の流れを作りましょう。
また工事契約書について知りたい方は、工事請負契約書の記載項目・役割・作成方法を解説した記事のご確認をお願いします。
支払い条件が明確になる
見積書には、代金の支払い時期や方法、分割・手付金の有無などの支払い条件を明記しておくことが重要です。これにより、発注者・受注者の双方で金銭トラブルを防ぐことができます。
とくに建設業では、着工前・中間・完工後と複数回に分けて支払いが行われるケースが多く、各工程ごとの支払いタイミングを明確にすることで「支払いの遅延」や「未払い」リスクを回避できます。
また、見積書に支払い条件を記載しておけば、契約書作成時のベースにもなり、契約交渉がスムーズになります。金額だけでなく、支払い条件までを明示することが信頼できる取引の第一歩です。
見積書の有効期限
見積書の有効期限は法的な定めがありません。一般的には、2週間〜6か月で設定している会社が多いです。
見積書の有効期間を短く設定すると、期限切れの度に発注者から発行を求められる可能性があり事務作業の手間がかかります。また有効期限の設定が長すぎると、先述した価格変動リスクに対応できないリスクがあるため注意が必要です。
見積書の有効期限にも法的な定めはない
見積書の有効期限は法的な定めがありません。一般的には、2週間〜6か月で設定している会社が多いです。なぜ見積書の有効期限が必要なのか、その意味や設定の目安、注意点を紹介します。
見積書の有効期限を設定する意味とは
見積書の有効期限設定が必要な理由は、見積発行事業者から契約締結を促すことを可能にするためです。万が一見積書に期限がない場合、施主がいつまでも契約へ動かず、待っている間に競合の建設事業者と契約してしまうような事態が起こりえます。しかし、有効期限を設定しておけば「そろそろ有効期限の時期ですが」と、先方へ決断を促しやすくなります。
見積書の有効期限の目安は2週間から半年
見積書の有効期限は一般的に、2週間から半年で設定する会社が多いです。施工の依頼は多額の金額が動く契約であり、あまりに短すぎると見積書の内容を熟慮する時間が足りないと考えられるためです。
有効期限に明確な定めはないため、上記の期間を目安として記載しましょう。
見積書の有効期限を決める際に注意すること
見積書の有効期間を短く設定すると、期限切れの度に発注者から発行を求められる可能性があり事務作業の手間がかかります。また有効期限の設定が長すぎると、先述した価格変動リスクに対応できないリスクがあるため注意が必要です。
見積書の作成はAnyONEで効率化
見積書の作成には、業務効率化システムの『AnyONE』がおすすめです。AnyONEは、階層構造で見積書が作成できるため、規模の大きい現場から小規模現場まであらゆる現場の見積書に対応します。
また操作感はエクセルと似ており、現在業務でエクセルを使用している会社であれば、乗り換えに手間はかかりません。エクセルで作成した見積書を活用して、簡単に新規見積書の作成が可能です。
AnyONEには、見積り作成以外にも以下の機能が備わっています。
【AnyONEの機能】
- 顧客管理
- 帳票管理
- 工事管理
- 物件管理
- 実行予算管理
- 支払い管理
- 請求・入金管理
- 図面・写真管理
- アフター・メンテナンス管理
AnyONEは、実行予算の作成にも対応しています。見積書の作成から実行予算作成、原価管理まで1つのシステムでおこなえるため、現場ごとの損益状況を細かく把握が可能です。1つのシステムでお金の流れを管理できると、どんぶり勘定から抜け出せます。情報が1箇所に集中するため、管理者や経営者はAnyONEを確認するだけで現場ごとの損益状況の把握が可能です。
またAnyONEは、インボイス(適格請求書)の出力にも対応しています。そのため、2023年10月以降も問題なく使い続けられるシステムです。
インボイスについて詳しく知りたい方は、インボイス制度に対応しないデメリットについて解説した記事をご確認ください。
AnyONE導入事例:ライトハウス株式会社
ライトハウス株式会社は、地域密着型の総合不動産企業として、住宅・店舗・事務所の設計から施工、アフターサービスまで一貫して手がけています。同社では以前、エクセルで見積書や請求書を作成していましたが、関数エラーや手入力による計算ミス、データ共有の煩雑さが課題となっていました。
AnyONE導入後は、見積書・請求書の作成時間が約1/10に短縮され、フォーマットの統一と情報共有の効率化を実現。計算ミスも大幅に減少しました。
また、アフターサービス機能により、点検予定やクレーム対応も迅速に行えるようになり、業務効率と顧客満足度の両立を実現しています。
詳しくはAnyONE導入事例「見積書や請求書作成での計算ミスが減少。作成時間が1/10にまで短縮されました。」をご覧ください。
まとめ
本記事では、見積書の法的拘束力や見積書が必要な理由、見積書の有効期限について解説しました。
建設業の見積書発行は建設業法第20条にて義務付けられています。また見積書が必要な理由は以下の3つです。
- 発注者との認識のズレをなくす
- 取引の客観的な証拠
- 取引の流れが明確になる
- 支払い条件を明確にする
見積書は、法的な裏付けだけでなく、信頼性の高い取引の基盤です。
効率的で正確な見積書を作成したい方には、工務店向け業務効率化システム「AnyONE」がおすすめです。エクセル感覚で使え、見積から請求・原価管理まで一元化できます。
まずは無料デモ体験や資料請求で、AnyONEの操作性と導入効果をご確認ください。
記事監修:佐藤主計
保有資格:1級造園施工管理技士、2級土木施工管理技士
建設業界に携わり30年。公共工事の主任技術者や現場代理人をはじめ、造園土木会社の営業マン・工事担当者として、数万円から数千万円の工事まで幅広く担当。施工実績は累計約350件にものぼる。